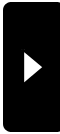ありがとう、しあわせ、おかげさま、そして感謝
ありがとう、しあわせ、おかげさま、そして感謝 
数多くのブログの中から
「長閑(のどか)な散歩」にご訪問くださり
厚く御礼申し上げます
 どうぞごゆっくりおくつろぎください
どうぞごゆっくりおくつろぎください 
2010年02月26日
あみだくじ
仏教豆知識30 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
あみだくじ
誰でも一度は引いたことがある「あみだくじ」。その「あみだくじ」の「あみだ」は、阿弥陀如来に由来し、さかのぼる事、室町時代から行われていたとのこと。つまり「あみだくじ」には700年近い歴史があるんですね。
しかし、当時の「あみだくじ」は現在の上から下へ降りていくものとは違い、真ん中から外に向かって放射状に人数分の線を書き、それを引くものでした。その形が阿弥陀如来の後光に似ていた事から「あみだくじ」と名前が付きました。

また、この「あみだくじ」にはハズレがありませんでした。一説には、阿弥陀如来は万人を平等に救うという教えから、全員が大小の違いはあるにせよ、何かしら引き当てることが出来るようにした為とも言われています。
さて、永田や仏壇店はおかげさまで今年で創業110年を迎えました。そこで創業110年特別イベントとして、「あみだくじ」ではなく「三角くじ」イベントを開催いたします。(笑)
店頭にて3000円以上お買い上げのお客さまにハズレナシの「三角くじ」が一本引けます。是非この機会に永田や仏壇店各店にご来店いただきますよう、心よりお待ちいたしております。

阿弥陀仏は光明なり
光明は智慧のかたちなり









仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP





















日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
あみだくじ
誰でも一度は引いたことがある「あみだくじ」。その「あみだくじ」の「あみだ」は、阿弥陀如来に由来し、さかのぼる事、室町時代から行われていたとのこと。つまり「あみだくじ」には700年近い歴史があるんですね。
しかし、当時の「あみだくじ」は現在の上から下へ降りていくものとは違い、真ん中から外に向かって放射状に人数分の線を書き、それを引くものでした。その形が阿弥陀如来の後光に似ていた事から「あみだくじ」と名前が付きました。

また、この「あみだくじ」にはハズレがありませんでした。一説には、阿弥陀如来は万人を平等に救うという教えから、全員が大小の違いはあるにせよ、何かしら引き当てることが出来るようにした為とも言われています。
さて、永田や仏壇店はおかげさまで今年で創業110年を迎えました。そこで創業110年特別イベントとして、「あみだくじ」ではなく「三角くじ」イベントを開催いたします。(笑)
店頭にて3000円以上お買い上げのお客さまにハズレナシの「三角くじ」が一本引けます。是非この機会に永田や仏壇店各店にご来店いただきますよう、心よりお待ちいたしております。

如月のことば
阿弥陀仏は光明なり
光明は智慧のかたちなり
「唯信鈔文意」








《ちょっと当社ネットショップのご紹介》

仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP







《ちょっと当社ヤフオクストアのご紹介》
| Gel Gems をお探しなら やすらぎ SHOP | アロマキャンドル をお探しなら やすらぎ SHOP | 和雑貨 をお探しなら やすらぎ SHOP | 仏壇仏具数珠 をお探しなら やすらぎ SHOP |














タグ :豆知識
2010年01月01日
殊勝(しゅしょう)
あけましておめでとうございます。
旧年中はたいへんお世話になりました。本年もこの「長閑な散歩」をどうぞよろしくお願い申し上げます。

仏教豆知識29 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
殊勝(しゅしょう)
もともと仏教語である「殊勝」とは文字通り「殊に勝れている」という意味。「殊」とは普通と違うこと。しかし、現在では「もっともらしい様子で神妙にしていること」などの意味合いで使われていることが多いようです。
「殊勝」を辞書で調べてみると「年齢や経歴の割りに立派なところがあり、褒めるに値する様子」と説明されています。
本来の意味と普段使われている内容が若干違う場合が多々ある今日この頃。謝罪会見などで「殊勝な顔をしている」場合、辞書に説明されているように「褒めるに値する様子」では少しおかしく「神妙にしている」と捉えた方が良いでしょう。
ちなみに「殊勝な気」とは場の雰囲気が甚だ厳粛なこと。年の初めは「殊勝な気」が自ずと満ちているものです。この気を心のどこかに留め、年の瀬まで忘れることなく、新しい年を元気に送りたいものですね。

睦月のことば
往生というは
浄土に
生るというなり
「尊号真像銘文」








《ちょっと当社ネットショップのご紹介》

仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP







《ちょっと当社ヤフオクストアのご紹介》
| Gel Gems をお探しなら やすらぎ SHOP | アロマキャンドル をお探しなら やすらぎ SHOP | 和雑貨 をお探しなら やすらぎ SHOP | 仏壇仏具数珠 をお探しなら やすらぎ SHOP |














タグ :豆知識
2009年12月31日
大晦日
仏教豆知識28 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
大晦日(おおみそか)
「大晦日」の由来は一年の最後の月の最終日である事からつけられました。旧暦では毎月の最終日を「晦日(みそか)」または「つごもり」といい、「月の最終日」を意味します。
昔は、深夜の零時ではなく、陽が沈むと一日が終わると考えられていた為、大晦日の日没が新年のスタートに該当しました。
その為、前日(大晦日の夕方)までにはお正月の準備を整え、大晦日は心身を清めて神社にこもり、一晩中起きて歳神様を迎えるのが習わしでした。
これは、新年のスタートでもある大晦日の晩に、歳神様をお迎えする前に寝てしまっては失礼にあたると考えられ、白髪やしわが増えるという言い伝えがあったからです。また、起きてお迎えできたら歳神様の力を授かるという習わしもありました。

今年一年、皆さまにはこの「長閑な散歩」に幾度とご訪問いただき、たいへんお世話になりました。ありがとうございます!
また来年もこの「長閑な散歩」、そしてCOOをどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは皆さま!良いお年をお迎えください!

年年歳歳
(ねんねんさいさい)









仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP





















日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
大晦日(おおみそか)
「大晦日」の由来は一年の最後の月の最終日である事からつけられました。旧暦では毎月の最終日を「晦日(みそか)」または「つごもり」といい、「月の最終日」を意味します。
昔は、深夜の零時ではなく、陽が沈むと一日が終わると考えられていた為、大晦日の日没が新年のスタートに該当しました。
その為、前日(大晦日の夕方)までにはお正月の準備を整え、大晦日は心身を清めて神社にこもり、一晩中起きて歳神様を迎えるのが習わしでした。
これは、新年のスタートでもある大晦日の晩に、歳神様をお迎えする前に寝てしまっては失礼にあたると考えられ、白髪やしわが増えるという言い伝えがあったからです。また、起きてお迎えできたら歳神様の力を授かるという習わしもありました。
《ゆたかニュースより》

今年一年、皆さまにはこの「長閑な散歩」に幾度とご訪問いただき、たいへんお世話になりました。ありがとうございます!
また来年もこの「長閑な散歩」、そしてCOOをどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは皆さま!良いお年をお迎えください!

今日の「四字熟語」
年年歳歳
(ねんねんさいさい)
来る年も来る年も。
毎年毎年、また、そのように毎年同じことが繰り返されるさま。
また来年の大晦日もこうして
「長閑な散歩」から皆さまに
ご挨拶ができますように。。。
毎年毎年、また、そのように毎年同じことが繰り返されるさま。
また来年の大晦日もこうして
「長閑な散歩」から皆さまに
ご挨拶ができますように。。。








《ちょっと当社ネットショップのご紹介》

仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP







《ちょっと当社ヤフオクストアのご紹介》
| Gel Gems をお探しなら やすらぎ SHOP | アロマキャンドル をお探しなら やすらぎ SHOP | 和雑貨 をお探しなら やすらぎ SHOP | 仏壇仏具数珠 をお探しなら やすらぎ SHOP |














タグ :豆知識
2009年12月15日
自然(じねん)
仏教豆知識27 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
自然(じねん)
「自然(しぜん)」とは「大自然」など、草木や雨風など、外的環境のことを指します。しかし、仏教では「じねん」と読み、「自ら然る」、つまり人間の作為のないそのままの在り方を意味します。
法(真理)がそのままに現れていることを示す「法爾(ほうに)」とは同じ意味で、ふたつを合わせて「自然法爾(じねんほうに)」をいう四字熟語にもなっています。これは「然るべき状態」のことで、「身の程を知る」こと。

人生の中における悩みの8割は人間関係によるものと言われております。その人間関係に悩みがちな我々も自然の一部。他人の考えを自分の都合に合わせようとせず、「自分」も「他人」もすべてをあるがままに受け入れた上で自然体の関係を目指すのが良いのではないでしょうか。

自然法爾
(じねんほうに)









仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP





















日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
自然(じねん)
「自然(しぜん)」とは「大自然」など、草木や雨風など、外的環境のことを指します。しかし、仏教では「じねん」と読み、「自ら然る」、つまり人間の作為のないそのままの在り方を意味します。
法(真理)がそのままに現れていることを示す「法爾(ほうに)」とは同じ意味で、ふたつを合わせて「自然法爾(じねんほうに)」をいう四字熟語にもなっています。これは「然るべき状態」のことで、「身の程を知る」こと。

人生の中における悩みの8割は人間関係によるものと言われております。その人間関係に悩みがちな我々も自然の一部。他人の考えを自分の都合に合わせようとせず、「自分」も「他人」もすべてをあるがままに受け入れた上で自然体の関係を目指すのが良いのではないでしょうか。

今日の「四字熟語」
自然法爾
(じねんほうに)
作為を捨ててありのままに任せること。
ほかからに力を加えないで、一切の存在はおのずから
真理にかなっているということ。
ほかからに力を加えないで、一切の存在はおのずから
真理にかなっているということ。








《ちょっと当社ネットショップのご紹介》

仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP







《ちょっと当社ヤフオクストアのご紹介》
| Gel Gems をお探しなら やすらぎ SHOP | アロマキャンドル をお探しなら やすらぎ SHOP | 和雑貨 をお探しなら やすらぎ SHOP | 仏壇仏具数珠 をお探しなら やすらぎ SHOP |














タグ :豆知識
2009年12月08日
譏嫌(きげん)
仏教豆知識26 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
譏嫌(きげん)
「今日の社長は機嫌が悪い」など、頻繁に使用される「機嫌」という言葉。この言葉はもともと「譏嫌」と書かれ、「譏り(そしり)」、「嫌う(きらう)」という意味を持ちます。
この言葉の由来は仏教の「譏嫌戒」。これは「お酒を飲んではいけない」「五辛(ごじん)(にんにく・にら・ねぎ・らっきょう・のびる)を食べてはいけない」など、自分を律するための教えを説いたものです。

良いことがあれば誰もが「機嫌」が良くなります。しかし、調子に乗りすぎ周りの人たちから「譏嫌」を招く、つまり「そしりきらわれる」ことのないよう、常に自分を戒める気持ちを忘れずに、他人の「機嫌」にも気を遣いたいものですね。










仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP





















日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
譏嫌(きげん)
「今日の社長は機嫌が悪い」など、頻繁に使用される「機嫌」という言葉。この言葉はもともと「譏嫌」と書かれ、「譏り(そしり)」、「嫌う(きらう)」という意味を持ちます。
この言葉の由来は仏教の「譏嫌戒」。これは「お酒を飲んではいけない」「五辛(ごじん)(にんにく・にら・ねぎ・らっきょう・のびる)を食べてはいけない」など、自分を律するための教えを説いたものです。

良いことがあれば誰もが「機嫌」が良くなります。しかし、調子に乗りすぎ周りの人たちから「譏嫌」を招く、つまり「そしりきらわれる」ことのないよう、常に自分を戒める気持ちを忘れずに、他人の「機嫌」にも気を遣いたいものですね。

今日の「四字熟語」
喜怒哀楽
(きどあいらく)
(きどあいらく)
喜び・怒り・悲しみ・楽しみ
人間が持っている様々な感情全般。
喜怒哀楽を押し殺す必要はありません。
しかし、他人の感情を無視して
それを出しすぎてもいけませんよね。
常に人を気遣う気持ちが大切だと思います。
人間が持っている様々な感情全般。
喜怒哀楽を押し殺す必要はありません。
しかし、他人の感情を無視して
それを出しすぎてもいけませんよね。
常に人を気遣う気持ちが大切だと思います。








《ちょっと当社ネットショップのご紹介》

仏壇仏具通販ネットショップ
NAGATAYAまごころSHOP







《ちょっと当社ヤフオクストアのご紹介》
| Gel Gems をお探しなら やすらぎ SHOP | アロマキャンドル をお探しなら やすらぎ SHOP | 和雑貨 をお探しなら やすらぎ SHOP | 仏壇仏具数珠 をお探しなら やすらぎ SHOP |














タグ :豆知識
2009年03月22日
仏教の豆知識 言葉編
このCOOのブログ「長閑な散歩」を開設し、1年と半年近くが経過しました。開設した当初は仏壇屋らしい記事をアップしていたのですが。。。
今年もお彼岸のことを!と、思いましたが記事の内容が過去記事とタブってしまうため、アップを断念!(笑)
スミマセンが。。。お彼岸の説明は過去記事リンクでお願いします!(汗)
お彼岸について
さて。。。タイトルの「仏教の豆知識 言葉編」!これまで様々な「仏教から出た日常語」をご紹介してまいりました。そろそろ新しい言葉を!と、思っていたのですが。。。
たくさん記事にしてまいりましたので、ご紹介した言葉かそうでない言葉なのか???ちょっとCOO自信もわからなくなってきてしまいました!
そんなわけで今日は過去にご紹介いたしました言葉のまとめ記事を作成させていただきます!

以心伝心
挨拶
安心
図に乗る
一蓮托生
金輪際
御馳走
因果因業因縁
日日是好日
有頂天
有り難い
色即是空
我慢
愚痴
退屈
油断
お陰様
往生
悪口
一期一会
堪能
醍醐味
自由
阿吽
劫
こうしてみると、色んな言葉を記事にしてきましたねぇ。。。
気なる言葉がございましたら、クリックして過去記事をご覧下さいね!



今年もお彼岸のことを!と、思いましたが記事の内容が過去記事とタブってしまうため、アップを断念!(笑)
スミマセンが。。。お彼岸の説明は過去記事リンクでお願いします!(汗)
お彼岸について
さて。。。タイトルの「仏教の豆知識 言葉編」!これまで様々な「仏教から出た日常語」をご紹介してまいりました。そろそろ新しい言葉を!と、思っていたのですが。。。
たくさん記事にしてまいりましたので、ご紹介した言葉かそうでない言葉なのか???ちょっとCOO自信もわからなくなってきてしまいました!
そんなわけで今日は過去にご紹介いたしました言葉のまとめ記事を作成させていただきます!

以心伝心
挨拶
安心
図に乗る
一蓮托生
金輪際
御馳走
因果因業因縁
日日是好日
有頂天
有り難い
色即是空
我慢
愚痴
退屈
油断
お陰様
往生
悪口
一期一会
堪能
醍醐味
自由
阿吽
劫
こうしてみると、色んな言葉を記事にしてきましたねぇ。。。
気なる言葉がございましたら、クリックして過去記事をご覧下さいね!

今日の「永田や COO」


2008年12月26日
劫(こう)
仏教豆知識25 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
劫(こう)
クリスマスも終り今年もあと僅かですね。またひとつ年を重ねてしまいます。。。
さて、「亀の甲より年の劫(功)」ということわざをご存知だと思います。これは「亀の甲」と「年の劫(功)」の語呂を合わせた洒落を用いたことわざですが、年長者の持つ経験や智恵を尊ぶことを意味しています。

この「劫」は仏教ではとても長い時間のことを指します。終りのないほどの長い時間を「永劫(えいごう)」、長い時間を要することを面倒がることを「億劫(おっくう)」と言います。
年を重ねるごとに年長者になってしまうCOO。その経験や智恵があとから来る者に少しでも役に立てるよう、少しでも頼ってもらえるよう来年も日々精進したいと思います。


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
劫(こう)
クリスマスも終り今年もあと僅かですね。またひとつ年を重ねてしまいます。。。
さて、「亀の甲より年の劫(功)」ということわざをご存知だと思います。これは「亀の甲」と「年の劫(功)」の語呂を合わせた洒落を用いたことわざですが、年長者の持つ経験や智恵を尊ぶことを意味しています。

この「劫」は仏教ではとても長い時間のことを指します。終りのないほどの長い時間を「永劫(えいごう)」、長い時間を要することを面倒がることを「億劫(おっくう)」と言います。
年を重ねるごとに年長者になってしまうCOO。その経験や智恵があとから来る者に少しでも役に立てるよう、少しでも頼ってもらえるよう来年も日々精進したいと思います。

「B型COO」今日のひと言自分説明
童話 『つるの恩返し』
助けてくれたらお礼をします。
つるがB型だったら。

やるやる。無償で助けてくれたら、なんとか恩返しします。
ありがとね助けてくれて。
だけど、やっぱり、はた織り姿は見せたくない。
助けてくれたらお礼をします。
つるがB型だったら。

やるやる。無償で助けてくれたら、なんとか恩返しします。
ありがとね助けてくれて。
だけど、やっぱり、はた織り姿は見せたくない。
『B型自分の説明書』より

タグ :豆知識
2008年10月10日
阿吽の呼吸
仏教豆知識24 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
阿吽(あうん)
「阿吽(あうん)」とは吐く息と吸う息。2人以上がひとつのことをするときの、微妙なタイミングやリズムが合うこと、息がピッタリ合うことを表します。
この「阿」と「吽」は、梵語の最初と最後の文字。「阿」は口を開き、「吽」は口を閉じて発することから、呼気と吸気の意味となり、両者が息を合わせるという意味につながりました。日本語の「あいうえお」で始まる五十音は、この梵語の配列を参考に考えられたものといわれています。
また、「阿」は悟りを求める菩提心、「吽」はその結果としての涅槃とされ、物事の始まりと終りを象徴します。赤ちゃんが「おぎゃー!」と泣きながら産まれ、そして歳を取り、口を閉じて亡くなっていく。人間の一生をも象徴しているのかもしれません。

誰かと何かをするとき、自分の考えだけで行動するのではなく、相手のことを思いやり、考えながら相手と気持ちを合わせること、まさに「阿吽の呼吸」が良い結果を生み出してくれるのではないでしょうか。
また、この「阿吽の呼吸」で仕事ができるビジネスパートナーを多く持つ経営者はイザというとき強いものです。お陰さまでCOOもたくさんの良きパートナーに恵まれています。そんなパートナーは一生大切にしたいものですね!


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
阿吽(あうん)
「阿吽(あうん)」とは吐く息と吸う息。2人以上がひとつのことをするときの、微妙なタイミングやリズムが合うこと、息がピッタリ合うことを表します。
この「阿」と「吽」は、梵語の最初と最後の文字。「阿」は口を開き、「吽」は口を閉じて発することから、呼気と吸気の意味となり、両者が息を合わせるという意味につながりました。日本語の「あいうえお」で始まる五十音は、この梵語の配列を参考に考えられたものといわれています。
また、「阿」は悟りを求める菩提心、「吽」はその結果としての涅槃とされ、物事の始まりと終りを象徴します。赤ちゃんが「おぎゃー!」と泣きながら産まれ、そして歳を取り、口を閉じて亡くなっていく。人間の一生をも象徴しているのかもしれません。

誰かと何かをするとき、自分の考えだけで行動するのではなく、相手のことを思いやり、考えながら相手と気持ちを合わせること、まさに「阿吽の呼吸」が良い結果を生み出してくれるのではないでしょうか。
また、この「阿吽の呼吸」で仕事ができるビジネスパートナーを多く持つ経営者はイザというとき強いものです。お陰さまでCOOもたくさんの良きパートナーに恵まれています。そんなパートナーは一生大切にしたいものですね!

「B型COO」今日のひと言自分説明
頼られると、ものすごくがんばる。
『B型自分の説明書』より

タグ :豆知識
2008年08月11日
自由
仏教豆知識23 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
自由(じゆう)
「自由(じゆう)」という言葉を辞書で調べてみると、『他からの制約や束縛を受けず、自分の意思・感情に従って行動すること』と記載されています。確かに「自由」はその通りの意味として使用されていますね。
しかし、仏教でいう「自由」は少しその意味合いが異なります。
「自由」の「由」は『そこを通って、他の場所へ行く』の意。つまり、「自由」とは『他人に頼ることなく、ひとりで存在すること』となります。お釈迦さまは「自らをよりどころとし、他のものをよりどころとせずにあれ」と、説いています。

「言論の自由」など、個人の自由が主張される時代ですが、自由を主張するには自己責任が伴います。自由だから何を言っても良い、何を書いても良いわけではなく、そこには「社会秩序を乱すことなく」という言葉が隠されています。
自らにもとづく自由とは結構難しいものです。


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
自由(じゆう)
「自由(じゆう)」という言葉を辞書で調べてみると、『他からの制約や束縛を受けず、自分の意思・感情に従って行動すること』と記載されています。確かに「自由」はその通りの意味として使用されていますね。
しかし、仏教でいう「自由」は少しその意味合いが異なります。
「自由」の「由」は『そこを通って、他の場所へ行く』の意。つまり、「自由」とは『他人に頼ることなく、ひとりで存在すること』となります。お釈迦さまは「自らをよりどころとし、他のものをよりどころとせずにあれ」と、説いています。

「言論の自由」など、個人の自由が主張される時代ですが、自由を主張するには自己責任が伴います。自由だから何を言っても良い、何を書いても良いわけではなく、そこには「社会秩序を乱すことなく」という言葉が隠されています。
自らにもとづく自由とは結構難しいものです。


タグ :豆知識
2008年07月16日
醍醐味
仏教豆知識22 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
醍醐味(だいごみ)
「映画の醍醐味」「ゴルフの醍醐味」「食べ歩きの醍醐味」などなど。「醍醐味」とは『その物事を深く経験して得られる他の何ものにも代えることのできないよさ』のことを言います。

「涅槃経」に、『我と無我(悟り)の関係は、乳から醍醐が熟成精製されるのと同様である。』という記述があります。
牛乳を精製していくとその味は乳味(にゅうみ)→酪味(らくみ)→生酥味(しょうそみ)→熟酥味(じゅくそみ)と、しだいに美味なものに変化をし、最後に最高の醍醐味になるとされています。
乳から醍醐が生じるように、悟りにも経るべき道筋があると仏教では教えています。つまり。。。100以上も叩くCOOが「ゴルフの醍醐味」を語るなんぞ、100万年も早いということです!



日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
醍醐味(だいごみ)
「映画の醍醐味」「ゴルフの醍醐味」「食べ歩きの醍醐味」などなど。「醍醐味」とは『その物事を深く経験して得られる他の何ものにも代えることのできないよさ』のことを言います。

「涅槃経」に、『我と無我(悟り)の関係は、乳から醍醐が熟成精製されるのと同様である。』という記述があります。
牛乳を精製していくとその味は乳味(にゅうみ)→酪味(らくみ)→生酥味(しょうそみ)→熟酥味(じゅくそみ)と、しだいに美味なものに変化をし、最後に最高の醍醐味になるとされています。
乳から醍醐が生じるように、悟りにも経るべき道筋があると仏教では教えています。つまり。。。100以上も叩くCOOが「ゴルフの醍醐味」を語るなんぞ、100万年も早いということです!



タグ :豆知識
2008年07月09日
堪能
仏教豆知識21 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
堪能(たんのう)
「美味しいものを堪能した。」「あの人は語学に堪能な人。」など、「学芸に優れている」「十分満足する」という意味で、「堪能」は日常的に使われる言葉のひとつです。しかしこの「堪能」も仏教用語のひとつで、「カンノウ」と発音し、そしてその意味は文字通り「堪える能力」のことを指します。
中国隋代の高僧・智顗(ちぎ)は、「魔訶止観(まかしかん)」に「勝れたる堪能を得る。名づけて力となす」と記しています。
何事もその道を習熟するには堪能(かんのう)が必要であり、そこから得られた結果もまた堪能(たんのう)である、というわけです。

堪える力がなくては学んだり目標を達成することは何ひとつできないでしょう。困難に堪えるからこそ、その結果手にするものには何ものにも代え難い価値があるのではないでしょうか。


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
堪能(たんのう)
「美味しいものを堪能した。」「あの人は語学に堪能な人。」など、「学芸に優れている」「十分満足する」という意味で、「堪能」は日常的に使われる言葉のひとつです。しかしこの「堪能」も仏教用語のひとつで、「カンノウ」と発音し、そしてその意味は文字通り「堪える能力」のことを指します。
中国隋代の高僧・智顗(ちぎ)は、「魔訶止観(まかしかん)」に「勝れたる堪能を得る。名づけて力となす」と記しています。
何事もその道を習熟するには堪能(かんのう)が必要であり、そこから得られた結果もまた堪能(たんのう)である、というわけです。

堪える力がなくては学んだり目標を達成することは何ひとつできないでしょう。困難に堪えるからこそ、その結果手にするものには何ものにも代え難い価値があるのではないでしょうか。


タグ :豆知識
2008年06月20日
一期一会
仏教豆知識20 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
一期一会(いちごいちえ)
誰でも知っているこの「一期一会」という言葉は江戸時代、井伊直弼が「お互いにもう会うことはないとしても、茶席では主人と客人はお互いに誠意をもって接するべき」と説いたことから広まりました。
「一期」とはひとの一生、「一会」とは唯一ただ一度の出会いのこと。「一期一会」とはひととの一度きりの出会いも大切にしようという意味です。
たびたび顔を合わせる相手であっても、今日の打ち合わせ、今日のデート、今日の出会いは二度と同じ時間を持つことはできない、人生でたった一度きりの大切で貴重な時間なのです。
ひとは一生涯のうちにいったい何人のひとと出会うことができるのでしょう。そのかけがえのない出会いを大切に、二度と来ない人生のひとときを共に過ごしながら「素敵な出会いだった」「とても楽しい時間だった」と思えることができたら、こんなに素晴らしいことはないと思いませんか。

自分はこのブログを通じて出会うことのできた皆さんとも、そんな有意義なひとときを過ごすことができたらこの上なく嬉しく思います。


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
一期一会(いちごいちえ)
誰でも知っているこの「一期一会」という言葉は江戸時代、井伊直弼が「お互いにもう会うことはないとしても、茶席では主人と客人はお互いに誠意をもって接するべき」と説いたことから広まりました。
「一期」とはひとの一生、「一会」とは唯一ただ一度の出会いのこと。「一期一会」とはひととの一度きりの出会いも大切にしようという意味です。
たびたび顔を合わせる相手であっても、今日の打ち合わせ、今日のデート、今日の出会いは二度と同じ時間を持つことはできない、人生でたった一度きりの大切で貴重な時間なのです。
ひとは一生涯のうちにいったい何人のひとと出会うことができるのでしょう。そのかけがえのない出会いを大切に、二度と来ない人生のひとときを共に過ごしながら「素敵な出会いだった」「とても楽しい時間だった」と思えることができたら、こんなに素晴らしいことはないと思いませんか。

自分はこのブログを通じて出会うことのできた皆さんとも、そんな有意義なひとときを過ごすことができたらこの上なく嬉しく思います。


タグ :豆知識
2008年06月15日
悪口
仏教豆知識19 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
悪口(あっく)
「悪口」と書いて「あっく」と読みます。「悪口」は仏教において行なってはならない十の悪業(十悪)のひとつ。十悪とは身・口・意から生じる十の汚れのことを指し、身・口・意を三毒と呼びます。
三毒のひとつ、口の汚れには「妄語・もうご」(嘘)、「綺語・きご」(真実ではない、飾り立てた言葉)、「両舌・りょうぜつ」(相手によって違ったことをいう、いわゆる二枚舌のこと)、そして「悪口・あっく」(他人は卑下し、傷つけるような言葉)の四悪業があります。

他人の誹謗、中傷は自らの人間性を低めてしまうだけでなく、昔から「口はわざわいのもと」と言われたように、ちょっとした「悪口」が災いして大変な結果を招きかねません。それが因果応報というものです。


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
悪口(あっく)
「悪口」と書いて「あっく」と読みます。「悪口」は仏教において行なってはならない十の悪業(十悪)のひとつ。十悪とは身・口・意から生じる十の汚れのことを指し、身・口・意を三毒と呼びます。
三毒のひとつ、口の汚れには「妄語・もうご」(嘘)、「綺語・きご」(真実ではない、飾り立てた言葉)、「両舌・りょうぜつ」(相手によって違ったことをいう、いわゆる二枚舌のこと)、そして「悪口・あっく」(他人は卑下し、傷つけるような言葉)の四悪業があります。

他人の誹謗、中傷は自らの人間性を低めてしまうだけでなく、昔から「口はわざわいのもと」と言われたように、ちょっとした「悪口」が災いして大変な結果を招きかねません。それが因果応報というものです。


タグ :豆知識
2008年05月28日
往生(おうじょう)
仏教豆知識18 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
往生(おうじょう)
「往生」は色々な使われ方をされている仏教語のひとつです。たとえば「電車が雪で立ち往生した。」とか「往生際が悪い!」など、あまり良い意味では使用されておりませんが、本来の「往生」の意味はどんな意味があるのでしょう。

「往生」を辞書で調べてみると、次のような意味が載っています。
1.極楽に生まれること。
2.死ぬこと。
3.あきらめて、じたばたしないこと。
4.処置に困ること。閉口。
もともと「往生」とは1番の現世を去って仏の世界である極楽浄土に生まれること。つまり輪廻転生(りんねてんしょう)することを意味します。
本来はとてもありがたいことなのですが、死ななければ極楽浄土へ行くことはできません。そんな理由から2番の死ぬことそのものも「往生」の意味として使われるようになりました。更に、あきらめること、閉口することと、意味は次第に広義へと移っていったようです。
時が流れるにつれ、言葉の意味もどんどん変わっていくんですね!


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
往生(おうじょう)
「往生」は色々な使われ方をされている仏教語のひとつです。たとえば「電車が雪で立ち往生した。」とか「往生際が悪い!」など、あまり良い意味では使用されておりませんが、本来の「往生」の意味はどんな意味があるのでしょう。

「往生」を辞書で調べてみると、次のような意味が載っています。
1.極楽に生まれること。
2.死ぬこと。
3.あきらめて、じたばたしないこと。
4.処置に困ること。閉口。
もともと「往生」とは1番の現世を去って仏の世界である極楽浄土に生まれること。つまり輪廻転生(りんねてんしょう)することを意味します。
本来はとてもありがたいことなのですが、死ななければ極楽浄土へ行くことはできません。そんな理由から2番の死ぬことそのものも「往生」の意味として使われるようになりました。更に、あきらめること、閉口することと、意味は次第に広義へと移っていったようです。
時が流れるにつれ、言葉の意味もどんどん変わっていくんですね!


タグ :豆知識
2008年05月03日
おかげさま
仏教豆知識17 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
お陰様(おかげさま)
「お陰様です!」。自分もとてもよく使う言葉のひとつですが、皆さまも感謝の気持ちを伝える言葉として日常的に口にしているのではないでしょうか。そもそも「お陰様」の「お陰」は、神仏の助けや加護のことを指しています。

「東方を拝むときは父母に感謝し、南方を拝むときは師に感謝し、西方は家族に、北方は友人に、上方は沙門(しゃもん)に、下方は目下のもののご苦労に感謝せよ。」と、教えを説いたのはお釈迦さまです。
万物は相互に関係しあい、たくさんの支えを受けながら我々は生かされてます。永田や仏壇店の「陰影礼讃」にはまさしくその教えを凝縮した意味合いが含まれています。
「お陰様」。本当に良い言葉ですね。



日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
お陰様(おかげさま)
「お陰様です!」。自分もとてもよく使う言葉のひとつですが、皆さまも感謝の気持ちを伝える言葉として日常的に口にしているのではないでしょうか。そもそも「お陰様」の「お陰」は、神仏の助けや加護のことを指しています。

「東方を拝むときは父母に感謝し、南方を拝むときは師に感謝し、西方は家族に、北方は友人に、上方は沙門(しゃもん)に、下方は目下のもののご苦労に感謝せよ。」と、教えを説いたのはお釈迦さまです。
万物は相互に関係しあい、たくさんの支えを受けながら我々は生かされてます。永田や仏壇店の「陰影礼讃」にはまさしくその教えを凝縮した意味合いが含まれています。
「お陰様」。本当に良い言葉ですね。



2008年04月20日
油断
仏教豆知識16 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
油断(ゆだん)
「油断大敵」など、「油断」と言う言葉は日常的によく使われますね。「油断」の意味を辞書で調べると、「気をゆるして、必要な注意を怠ること」と、記載されておりました。では、何故この「油を断つ」がそんな意味になったのでしょう?

昔々、ある王が家臣に油を入れた鉢を持たせて人通りの多い道を歩かせ、「もし油を一滴でもこぼしたら、命を断つ!」と、その家臣に言い渡したと、「涅槃経」と言う経本に書かれています。
一瞬の気の緩みから「油」が原因で命を「断たれる」と言う意味からそれを「油断」と呼んだことに由来しているのです。つまり、「油を断つ」のではなく、「油が原因で命が断たれる」だったのですね!
油をこぼしたくらいで命を断たれたら一生後悔しそうです。油断大敵!油断しないように慎重に慎重に! (^^;)


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
油断(ゆだん)
「油断大敵」など、「油断」と言う言葉は日常的によく使われますね。「油断」の意味を辞書で調べると、「気をゆるして、必要な注意を怠ること」と、記載されておりました。では、何故この「油を断つ」がそんな意味になったのでしょう?

昔々、ある王が家臣に油を入れた鉢を持たせて人通りの多い道を歩かせ、「もし油を一滴でもこぼしたら、命を断つ!」と、その家臣に言い渡したと、「涅槃経」と言う経本に書かれています。
一瞬の気の緩みから「油」が原因で命を「断たれる」と言う意味からそれを「油断」と呼んだことに由来しているのです。つまり、「油を断つ」のではなく、「油が原因で命が断たれる」だったのですね!
油をこぼしたくらいで命を断たれたら一生後悔しそうです。油断大敵!油断しないように慎重に慎重に! (^^;)


タグ :豆知識
2008年04月05日
退屈
仏教豆知識15 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
退屈(たいくつ)
「退屈」とは、やることがなくて時間をもてあまし、その状況に嫌気がさしている様子。また、行なっていることについて関心を失い、飽きている様子。そしてその感情のことを言います。

しかし「退屈」はもともと仏教語で、文字通り仏道修行から退き、屈することを言います。やることがなくて時間をもてあますのではなく、やらなければならないことが大きすぎるため、その苦しさや難しさに屈してこころが退き、努力するこころを失うことを意味していました。
目指すべきものが大きければ大きいほど、その苦しさや難しさに立ち向かい努力しようとする強靭なこころを身に付けたいものですね!


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
退屈(たいくつ)
「退屈」とは、やることがなくて時間をもてあまし、その状況に嫌気がさしている様子。また、行なっていることについて関心を失い、飽きている様子。そしてその感情のことを言います。

しかし「退屈」はもともと仏教語で、文字通り仏道修行から退き、屈することを言います。やることがなくて時間をもてあますのではなく、やらなければならないことが大きすぎるため、その苦しさや難しさに屈してこころが退き、努力するこころを失うことを意味していました。
目指すべきものが大きければ大きいほど、その苦しさや難しさに立ち向かい努力しようとする強靭なこころを身に付けたいものですね!


タグ :豆知識
2008年04月01日
愚痴
仏教豆知識14 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
愚痴(ぐち)
「俺の部下は働きが悪い!」とか、「俺の上司は理解がない!」など、口に出してもしかたのないことなのについついこぼしてしまう愚痴。しかし仏教でいう「愚痴」は、「仏の智慧に暗い」という根本的無知のことを言います。
「愚痴」は108種の煩悩のなかでもとくに強力なものとされている三毒のひとつに位置づけられています。三毒とは「貪欲(とんよく)」(むさぼり欲しがるこころ)、「瞋恚(しんに)」(いかり腹立つこころ)、そして「愚痴」(真理に対する無知のこころ)です。
「愚痴」は目先のものにとらわれ、そのものの本質を理解する能力のない愚かなこころを指しています。ですから「愚痴」をこぼしすぎて自分のそんなこころの一面を他人にさらけださないように!
釈迦は「人間が苦悩する原因は、こころをおおう煩悩にある」と説いています。自分もいつまでたっても色んな煩悩を消し去ることができません。まあ、人間ですから当たり前なのですが。だからこそ毎日が勉強です!


日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
愚痴(ぐち)
「俺の部下は働きが悪い!」とか、「俺の上司は理解がない!」など、口に出してもしかたのないことなのについついこぼしてしまう愚痴。しかし仏教でいう「愚痴」は、「仏の智慧に暗い」という根本的無知のことを言います。
「愚痴」は108種の煩悩のなかでもとくに強力なものとされている三毒のひとつに位置づけられています。三毒とは「貪欲(とんよく)」(むさぼり欲しがるこころ)、「瞋恚(しんに)」(いかり腹立つこころ)、そして「愚痴」(真理に対する無知のこころ)です。
「愚痴」は目先のものにとらわれ、そのものの本質を理解する能力のない愚かなこころを指しています。ですから「愚痴」をこぼしすぎて自分のそんなこころの一面を他人にさらけださないように!
釈迦は「人間が苦悩する原因は、こころをおおう煩悩にある」と説いています。自分もいつまでたっても色んな煩悩を消し去ることができません。まあ、人間ですから当たり前なのですが。だからこそ毎日が勉強です!


タグ :豆知識
2008年03月23日
我慢我慢!
仏教豆知識13 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
我慢(がまん)
言葉と言うのは長く使われているうちにその意味が変化してしまうことが多々あるようです。その中のひとつで「我慢」という言葉があります。「我慢」は一般的に良い意味で用いられます。「我慢」をすることは美徳とさえ思われています。しかし仏教でいう「我慢」は悪い意味で用いられていました。
「我慢」はサンスクリット語「mana(マーナ)」の漢訳で、自分の中心に我(が)があるとの考えから、「我をたのんで自らを高くし、他をあなどること」と説明しています。仏教ではそのようなおごりたかぶる7つのこころを「七慢(しちまん)」と呼んでいます。

七慢(しちまん)
高慢(こうまん)
他と比較しておごり高ぶること。自分の方が上だと思うこと。
過慢(かまん)
自分と同等のものに対して自分の方が上だと思うこと。
慢過慢(まんかまん)
自分より優れたものに対し、同等、またそれ以上だと思い誤ること。
我慢(がまん)
自分の考えに執着し、考えが変わらないと思い上がること。
増上慢(じょうぞうまん)
悟りの域に達していないのにすでに悟った、極意を得たと自惚れること。
卑慢(ひまん)
はるかに優れたものに対し、自分は少ししか劣っていないと思うこと。
邪慢(じゃまん)
間違った行いをしても正しいことをしたと言い張ること。徳があると思い込むこと。
このように思い上がることなく、自惚れることなく、素直に、そして謙虚に生きていきたいものですね! (^。^)/

日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
我慢(がまん)
言葉と言うのは長く使われているうちにその意味が変化してしまうことが多々あるようです。その中のひとつで「我慢」という言葉があります。「我慢」は一般的に良い意味で用いられます。「我慢」をすることは美徳とさえ思われています。しかし仏教でいう「我慢」は悪い意味で用いられていました。
「我慢」はサンスクリット語「mana(マーナ)」の漢訳で、自分の中心に我(が)があるとの考えから、「我をたのんで自らを高くし、他をあなどること」と説明しています。仏教ではそのようなおごりたかぶる7つのこころを「七慢(しちまん)」と呼んでいます。

七慢(しちまん)
高慢(こうまん)
他と比較しておごり高ぶること。自分の方が上だと思うこと。
過慢(かまん)
自分と同等のものに対して自分の方が上だと思うこと。
慢過慢(まんかまん)
自分より優れたものに対し、同等、またそれ以上だと思い誤ること。
我慢(がまん)
自分の考えに執着し、考えが変わらないと思い上がること。
増上慢(じょうぞうまん)
悟りの域に達していないのにすでに悟った、極意を得たと自惚れること。
卑慢(ひまん)
はるかに優れたものに対し、自分は少ししか劣っていないと思うこと。
邪慢(じゃまん)
間違った行いをしても正しいことをしたと言い張ること。徳があると思い込むこと。
このように思い上がることなく、自惚れることなく、素直に、そして謙虚に生きていきたいものですね! (^。^)/

タグ :豆知識
2008年03月22日
色即是空
仏教豆知識12 -仏教から出た日常語-
日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
色即是空(しきそくぜくう)
仏教には数多くのお経があり、それぞれの宗派ごとに最も大切なお経(根本経典)が決められています。しかし、日本人に最も親しまれているお経は、特定の宗派の根本経典となっていない「般若心経(はんにゃしんぎょう)」ではないでしょうか。この「般若心経」のなかの「色即是空 空即是色」というフレーズは誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この「色即是空 空即是色」とは、「色は即ち是れ空。空は即ち是れ色」と読みくだし、この世に存在するすべてのものは因と縁によって存在しているだけで、実態ではなく無であるということ。つまり「目に見え、手でふれることができるものだけにこころをとらわれてはいけない」ということです。
欲望にこころをとらわれることなく、こころ豊かにいまこの世に存在できている自分の命を大切にし、そして感謝したいものですね。

日常で使用している言葉の中には仏教から出たものが多くありますが
案外知られていないようです。その中からごく身近なものをシリーズで
紹介していきたいと思います。
色即是空(しきそくぜくう)
仏教には数多くのお経があり、それぞれの宗派ごとに最も大切なお経(根本経典)が決められています。しかし、日本人に最も親しまれているお経は、特定の宗派の根本経典となっていない「般若心経(はんにゃしんぎょう)」ではないでしょうか。この「般若心経」のなかの「色即是空 空即是色」というフレーズは誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この「色即是空 空即是色」とは、「色は即ち是れ空。空は即ち是れ色」と読みくだし、この世に存在するすべてのものは因と縁によって存在しているだけで、実態ではなく無であるということ。つまり「目に見え、手でふれることができるものだけにこころをとらわれてはいけない」ということです。
欲望にこころをとらわれることなく、こころ豊かにいまこの世に存在できている自分の命を大切にし、そして感謝したいものですね。