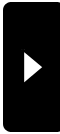ありがとう、しあわせ、おかげさま、そして感謝
ありがとう、しあわせ、おかげさま、そして感謝 
数多くのブログの中から
「長閑(のどか)な散歩」にご訪問くださり
厚く御礼申し上げます
 どうぞごゆっくりおくつろぎください
どうぞごゆっくりおくつろぎください 
2008年07月03日
提灯について
盆には、霊に帰ってくる家を知らせる目印として、提灯に火を灯して飾るのが習わしになっています。提灯は、軒先に吊したり、精霊棚の両脇に飾って夜には点灯します。特に新盆を迎える家では、「初盆(新盆)提灯」という白張りの提灯を用意します。正式には新盆の家の家紋を入れた白い提灯がしきたりですが、この白い提灯は初盆の時にだけ使うもので、お盆が終わる時には送り火で焚いたり、壇那寺におさめたりしなくてはなりません。そこで最近では、あまり白張りにこだわらず、毎年使えるように絵柄のついた提灯を新盆の時にも飾ることが多くなりました。

新盆には、近親者や故人と縁の深かった知人や友人が、提灯を贈る例が多く見られます。しかし、最近では、住宅事情の関係で、たくさんの提灯を飾る場所がありません。ですから、贈る側はよく先方にうかがった上で、「御仏前(お初盆)」と表書きした金封を贈り、喪主に購入してもらうという方法もあります。いずれにしても、贈る時はお盆の1週間前までに届くように手配するのが礼儀です。なお、以前は、新盆の提灯は近親者から、その他の提灯は親戚や知人から贈るというのが正式でした。
また、浄土真宗には、霊魂が位牌に宿るとか、盆に帰ってくるという考え方はしないため、特に他の宗派のような新盆の行事もありません。したがって、新盆の提灯をお供えする習わしもありません。ただ、お提灯はお盆の風物詩的な存在になりつつあるため、浄土真宗の方でもお供えされているお宅は少なくありません。

お盆についての「仏事豆知識」。少しずつ紹介をしてまいりましたが、この「お提灯について」で完結になります。皆さまに少しでもお盆について知っていただき、お盆を迎えていただければ幸いに存じます。
お盆についての過去記事はこちらよりご覧下さい。
「お盆のいわれ」
「お盆のしきたり」
「棚経とお墓参り」
「お墓参りの仕方」
「新盆「初盆」の迎え方」



新盆には、近親者や故人と縁の深かった知人や友人が、提灯を贈る例が多く見られます。しかし、最近では、住宅事情の関係で、たくさんの提灯を飾る場所がありません。ですから、贈る側はよく先方にうかがった上で、「御仏前(お初盆)」と表書きした金封を贈り、喪主に購入してもらうという方法もあります。いずれにしても、贈る時はお盆の1週間前までに届くように手配するのが礼儀です。なお、以前は、新盆の提灯は近親者から、その他の提灯は親戚や知人から贈るというのが正式でした。
また、浄土真宗には、霊魂が位牌に宿るとか、盆に帰ってくるという考え方はしないため、特に他の宗派のような新盆の行事もありません。したがって、新盆の提灯をお供えする習わしもありません。ただ、お提灯はお盆の風物詩的な存在になりつつあるため、浄土真宗の方でもお供えされているお宅は少なくありません。

お盆についての「仏事豆知識」。少しずつ紹介をしてまいりましたが、この「お提灯について」で完結になります。皆さまに少しでもお盆について知っていただき、お盆を迎えていただければ幸いに存じます。
お盆についての過去記事はこちらよりご覧下さい。
「お盆のいわれ」
「お盆のしきたり」
「棚経とお墓参り」
「お墓参りの仕方」
「新盆「初盆」の迎え方」


2008年07月01日
新盆(初盆)の迎え方
故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん)」といいます。(三河地方では「初盆(はつぼん)」と言います。)喪明け前にお盆に入った場合は、翌年のお盆が新盆となります。故人は亡くなってから百か日まで、努力精進を続けながら霊界で過ごしておられます。この故人が、心から待ち望んでいる休息日が、新盆なのです。
新盆は故人の霊が初めて帰ってくるという言い伝えから、一般のお盆よりもねんごろに供養をします。親戚や縁者から盆堤灯が贈られ、軒先に新盆堤灯(地域によって異なるが、絵柄のない白張堤灯)を飾るのが正式だといわれています。通常の盆棚とは別に、新仏の祭壇を用意することもあります。霊前にはきまったお盆のお供えの他に、故人の好物なども供えましょう。これらの供物は、お墓にも供えます。お仏壇の灯明は絶やさないように気を配りましょう。

葬儀の時にお世話になった方や、親戚、知人、近親者を招き、壇那寺の僧侶を迎えて回向してもらいます。招待された方は「御仏前」もしくは「御供物料」を持参して霊前に供えます。僧侶には「御布施」を差し上げ、これに「御膳料」を添えるのが普通です。その後に、参会者全員で供養の意味で食事(お斎)をします。新盆の供養の時は、一般的に遺族は男女とも、正式喪服を着るのが習わしです。
壇那寺で営まれる精霊供養は、お寺がお盆の期間中、新盆の精霊を中心に信徒各家の寺位牌(本位牌)を精霊棚で供養し、お盆の最終日に送り火を焚く行事です。この時、灯籠流しのできない地域では、白木位牌を、その火で焚きます。
また、僧侶を自宅に招かず、家族でお墓参りに入った際に「御布施」を届け、供養をお願いする場合もあります。



新盆は故人の霊が初めて帰ってくるという言い伝えから、一般のお盆よりもねんごろに供養をします。親戚や縁者から盆堤灯が贈られ、軒先に新盆堤灯(地域によって異なるが、絵柄のない白張堤灯)を飾るのが正式だといわれています。通常の盆棚とは別に、新仏の祭壇を用意することもあります。霊前にはきまったお盆のお供えの他に、故人の好物なども供えましょう。これらの供物は、お墓にも供えます。お仏壇の灯明は絶やさないように気を配りましょう。

葬儀の時にお世話になった方や、親戚、知人、近親者を招き、壇那寺の僧侶を迎えて回向してもらいます。招待された方は「御仏前」もしくは「御供物料」を持参して霊前に供えます。僧侶には「御布施」を差し上げ、これに「御膳料」を添えるのが普通です。その後に、参会者全員で供養の意味で食事(お斎)をします。新盆の供養の時は、一般的に遺族は男女とも、正式喪服を着るのが習わしです。
壇那寺で営まれる精霊供養は、お寺がお盆の期間中、新盆の精霊を中心に信徒各家の寺位牌(本位牌)を精霊棚で供養し、お盆の最終日に送り火を焚く行事です。この時、灯籠流しのできない地域では、白木位牌を、その火で焚きます。
また、僧侶を自宅に招かず、家族でお墓参りに入った際に「御布施」を届け、供養をお願いする場合もあります。



2008年06月29日
お墓参りの仕方
今朝アップいたしました「棚経とお墓参り」の記事に、しましまさまより「お墓のお掃除の仕方」のご質問をいただきました。ので、さっそくご説明記事をアップいたします!

お盆やお彼岸には、多くの人がお墓参りをします。しかしそのとき以外にもお墓参りをしましょう。故人の事を思い出したとき、故人に何かを相談したいとき、あるいは故人の誕生日などにお墓参りをすることはとても良いことです。故人との思い出、故人への感謝の気持ちはいつまでも大切にしたいものです。
《用意をするもの》
お墓参りをする時、生花、線香、ローソク、マッチ、お供えなどを忘れずに持って行くようにしましょう。霊園の場合ならば、近くに生花店があることが多く、お墓にお供えするのに適した生花を購入することができます。またお供え物は故人が好んでいたものをご用意されるとよろしいでしょう。掃除用具やひしゃく、手桶なども必要ですが、お寺や霊園で備えているケースが多いようですね。
《お掃除の仕方》
墓前でご先祖さまにお参りする前には、必ずお掃除をしましょう。この時、ご先祖さまに対する奉仕の気持ちを忘れずにお掃除をすることが大切です。
まずはじめに、墓石の周囲の草むしりやゴミ拾いをします。次に墓石に水をかけて、たわしなどで丁寧に磨きます。汚れが目立つところがあれば、丹念に磨いて下さい。手の届かないような場所を磨くときには、礎石にのぼってもかまいません。文字が掘ってあるところのお掃除には、歯ブラシがあるといいでしょう。磨き終わったら、きれいな布で、水を拭き取って掃除終了です。
《お参りの作法》
まず花立てにお花を飾ります。次に用意した供物をお供えします。この時、供物は半紙の上に置くといいでしょう。そしてローソクに火を灯し、そこから線香に火をつけます。
お参りはひとりひとり行います。はじめに線香をお供えし、墓石に水をかけます。水は「清浄なもの」の象徴で、水をかけることによって、ご先祖さまの霊を清めるとされているのです。そしてご先祖さまに向かって、合掌し、冥福を祈ります。
お参りが終わったらお供えは鳥などに荒らされないよう、持ち帰るようにします。前回お参りに来たときの花などが残っていたら、ゴミ袋に入れて持ち帰ります。また古くなったお塔婆は、抜いて、墓地の焼却炉で懇ろにお焚きあげしてもらいます。
《お数珠もお忘れなく》
お墓参りをするときにはお数珠を手に、合掌をするのが作法です。お数珠は仏教徒のシンボルだといわれています。またそれ以上に、お数珠の珠には、ご先祖さまへの功徳を何倍にもする力があるとされているのです。それゆえお数珠を持ってお参りすることで、ご先祖さまへのよりよい供養ができるのです。



お盆やお彼岸には、多くの人がお墓参りをします。しかしそのとき以外にもお墓参りをしましょう。故人の事を思い出したとき、故人に何かを相談したいとき、あるいは故人の誕生日などにお墓参りをすることはとても良いことです。故人との思い出、故人への感謝の気持ちはいつまでも大切にしたいものです。
《用意をするもの》
お墓参りをする時、生花、線香、ローソク、マッチ、お供えなどを忘れずに持って行くようにしましょう。霊園の場合ならば、近くに生花店があることが多く、お墓にお供えするのに適した生花を購入することができます。またお供え物は故人が好んでいたものをご用意されるとよろしいでしょう。掃除用具やひしゃく、手桶なども必要ですが、お寺や霊園で備えているケースが多いようですね。
《お掃除の仕方》
墓前でご先祖さまにお参りする前には、必ずお掃除をしましょう。この時、ご先祖さまに対する奉仕の気持ちを忘れずにお掃除をすることが大切です。
まずはじめに、墓石の周囲の草むしりやゴミ拾いをします。次に墓石に水をかけて、たわしなどで丁寧に磨きます。汚れが目立つところがあれば、丹念に磨いて下さい。手の届かないような場所を磨くときには、礎石にのぼってもかまいません。文字が掘ってあるところのお掃除には、歯ブラシがあるといいでしょう。磨き終わったら、きれいな布で、水を拭き取って掃除終了です。
《お参りの作法》
まず花立てにお花を飾ります。次に用意した供物をお供えします。この時、供物は半紙の上に置くといいでしょう。そしてローソクに火を灯し、そこから線香に火をつけます。
お参りはひとりひとり行います。はじめに線香をお供えし、墓石に水をかけます。水は「清浄なもの」の象徴で、水をかけることによって、ご先祖さまの霊を清めるとされているのです。そしてご先祖さまに向かって、合掌し、冥福を祈ります。
お参りが終わったらお供えは鳥などに荒らされないよう、持ち帰るようにします。前回お参りに来たときの花などが残っていたら、ゴミ袋に入れて持ち帰ります。また古くなったお塔婆は、抜いて、墓地の焼却炉で懇ろにお焚きあげしてもらいます。
《お数珠もお忘れなく》
お墓参りをするときにはお数珠を手に、合掌をするのが作法です。お数珠は仏教徒のシンボルだといわれています。またそれ以上に、お数珠の珠には、ご先祖さまへの功徳を何倍にもする力があるとされているのです。それゆえお数珠を持ってお参りすることで、ご先祖さまへのよりよい供養ができるのです。


2008年06月29日
棚経とお墓参り
《棚経》
お盆にあげてもらうお経を「棚経」といいます。精霊棚の前であげるお経のことです。お経をあげる前に精霊棚を設けますが、精霊棚がない場合は、お仏壇を清掃してその前に台を設け、盆花、盆飾り、お供えを用意しましょう。
壇那寺の僧侶は、お盆の決められた期間中に、全ての檀家と信徒の家を訪ねて回向します。こうした全檀家信徒の家をお参りする風習は、江戸時代の「邪宗門改め」に基づくものとされています。棚経の時は、お経が始まるまでに家族全員が精霊棚の前に揃ってお参りします。礼を失することのない服装で、テレビやラジオは消しておきましょう。お布施の包みは、既製の不祝儀袋か半紙を折って、墨か黒インクで「御布施」と書きます。お布施は棚経が始まる前に、あらかじめ包んでおきましょう。
棚経は本来、精霊棚の入魂法要としての性格を持っています。先祖代々の諸精霊だけでなく、有縁・無縁の三界の万霊を供養する大切な法事と考えられています。なお、浄土真宗については、精霊棚などの特別のお飾りはせず、棚経も行いません。

《お盆のお墓参り》
まず、先祖の霊をお墓に迎えに行きます。お墓の掃除は、お盆の前日までにすませておきましょう。お墓で迎え火を焚き、「どうぞわが家へご案内します」と迎えます。お盆の期間中、わが家でくつろいだ先祖の霊は、お盆最後の夕方に、お墓まで送って行く気持ちをあらわして、送り火を家の前で焚きます。送り火を焚いた後、お墓にお参りし、冥福を祈ることも大切です。こうして、お盆は先祖の霊を送迎するためのお墓参りとともに、無縁仏への供養もあります。
自分につながる方々という思いで供養をすれば、日頃寂しいであろう無縁仏は喜ばれることでしょう。また、年忌法要などはもちろん、思い立った時にはいつでも先祖をたずね、お墓参りをしたいものです。



お盆にあげてもらうお経を「棚経」といいます。精霊棚の前であげるお経のことです。お経をあげる前に精霊棚を設けますが、精霊棚がない場合は、お仏壇を清掃してその前に台を設け、盆花、盆飾り、お供えを用意しましょう。
壇那寺の僧侶は、お盆の決められた期間中に、全ての檀家と信徒の家を訪ねて回向します。こうした全檀家信徒の家をお参りする風習は、江戸時代の「邪宗門改め」に基づくものとされています。棚経の時は、お経が始まるまでに家族全員が精霊棚の前に揃ってお参りします。礼を失することのない服装で、テレビやラジオは消しておきましょう。お布施の包みは、既製の不祝儀袋か半紙を折って、墨か黒インクで「御布施」と書きます。お布施は棚経が始まる前に、あらかじめ包んでおきましょう。
棚経は本来、精霊棚の入魂法要としての性格を持っています。先祖代々の諸精霊だけでなく、有縁・無縁の三界の万霊を供養する大切な法事と考えられています。なお、浄土真宗については、精霊棚などの特別のお飾りはせず、棚経も行いません。

《お盆のお墓参り》
まず、先祖の霊をお墓に迎えに行きます。お墓の掃除は、お盆の前日までにすませておきましょう。お墓で迎え火を焚き、「どうぞわが家へご案内します」と迎えます。お盆の期間中、わが家でくつろいだ先祖の霊は、お盆最後の夕方に、お墓まで送って行く気持ちをあらわして、送り火を家の前で焚きます。送り火を焚いた後、お墓にお参りし、冥福を祈ることも大切です。こうして、お盆は先祖の霊を送迎するためのお墓参りとともに、無縁仏への供養もあります。
自分につながる方々という思いで供養をすれば、日頃寂しいであろう無縁仏は喜ばれることでしょう。また、年忌法要などはもちろん、思い立った時にはいつでも先祖をたずね、お墓参りをしたいものです。



2008年06月27日
お盆のしきたり
《迎え火と送り火》
「迎え火」は、お盆の始まりの日の夕方に門や玄関の前、軒先などで焚く明りです。故人の精霊が家に帰ってくる時に道に迷わないようにとの願いから、陶器のおぼんや素焼きのほうろくなどにオガラ(麻の皮をはいだ茎)や白樺の皮、地方によっては藁を焚いて道標とします。墓地近くの家では、お墓参りをして、盆灯籠に火をつけてお迎えします。迎え火を焚いた後は、その火を移してお灯明をともし、盆堤灯の明りをつけます。
お盆の終わりの日の夕方には「迎え火」を焚いた同じ場所で、「送り火」を焚き、合掌礼拝し、帰る道を照らして精霊を送ります。墓地近くの家では、お墓参りすることは迎え火の時と同じです。
精霊流し(灯籠流し)は、お盆のお供え物やお飾りをのせた精霊舟(灯籠舟)に火をともして、川や海に流す行事です。川は山に発し、海に流れてゆくからでしょうか、灯籠を流す地域もあります。これは「精霊送り」と「送り火」を一緒にしたものです。

《精霊棚》
宗派や地方によって多少異なりますが、お盆を迎えるにあたり、お仏壇の前に「精霊棚」を設けます。精霊棚とは、「盆棚」「霊棚」「魂祭り棚」ともいい、お仏壇の前に置いた小机にゴザを敷いて作った棚です。ゴザは、手前の方は床に垂らしておきましょう。餓鬼道世界で苦しんで力の衰えた精霊でも、よじ登ってこられるように、との配慮からです。
棚の四隅に青竹を柱として立てて、上に「真菰の綱」を張り、盆花を吊します。先祖の精霊は普段、山頂や原野にあって子孫を見守っている、と考えられていたので、盆花は山野の草花がお飾りに使われます。真菰の綱は、この中にご先祖の霊が来るというしきりを作るためです。そして、真菰の簾のところには本尊や先祖代々の位牌を安置し、その前に三具足、もしくは五具足などの供養のための仏具を整えます。
霊前には、霊膳や盆花、野菜、果物、故人の好物を供え、キュウリにオガラを刺して作った馬、ナスにオガラを刺して作った牛などを飾ります。この馬と牛には、先祖の霊が馬に乗ってこの世に帰り、牛に乗ってあの世に戻る、という意味が込められています。(馬に乗ってなるべく早くこの世に帰り、牛に乗ってゆっくりゆっくりあの世に戻っていただく、という意味もあるようです。)
ただし、浄土真宗では、自分の善行や施物を死者に回向する「追善供養」の思想はありません。他界した人は阿弥陀如来の本願によって浄土に往生するという教義なので、迎え火、送り火、精霊棚などは行いません。



「迎え火」は、お盆の始まりの日の夕方に門や玄関の前、軒先などで焚く明りです。故人の精霊が家に帰ってくる時に道に迷わないようにとの願いから、陶器のおぼんや素焼きのほうろくなどにオガラ(麻の皮をはいだ茎)や白樺の皮、地方によっては藁を焚いて道標とします。墓地近くの家では、お墓参りをして、盆灯籠に火をつけてお迎えします。迎え火を焚いた後は、その火を移してお灯明をともし、盆堤灯の明りをつけます。
お盆の終わりの日の夕方には「迎え火」を焚いた同じ場所で、「送り火」を焚き、合掌礼拝し、帰る道を照らして精霊を送ります。墓地近くの家では、お墓参りすることは迎え火の時と同じです。
精霊流し(灯籠流し)は、お盆のお供え物やお飾りをのせた精霊舟(灯籠舟)に火をともして、川や海に流す行事です。川は山に発し、海に流れてゆくからでしょうか、灯籠を流す地域もあります。これは「精霊送り」と「送り火」を一緒にしたものです。

《精霊棚》
宗派や地方によって多少異なりますが、お盆を迎えるにあたり、お仏壇の前に「精霊棚」を設けます。精霊棚とは、「盆棚」「霊棚」「魂祭り棚」ともいい、お仏壇の前に置いた小机にゴザを敷いて作った棚です。ゴザは、手前の方は床に垂らしておきましょう。餓鬼道世界で苦しんで力の衰えた精霊でも、よじ登ってこられるように、との配慮からです。
棚の四隅に青竹を柱として立てて、上に「真菰の綱」を張り、盆花を吊します。先祖の精霊は普段、山頂や原野にあって子孫を見守っている、と考えられていたので、盆花は山野の草花がお飾りに使われます。真菰の綱は、この中にご先祖の霊が来るというしきりを作るためです。そして、真菰の簾のところには本尊や先祖代々の位牌を安置し、その前に三具足、もしくは五具足などの供養のための仏具を整えます。
霊前には、霊膳や盆花、野菜、果物、故人の好物を供え、キュウリにオガラを刺して作った馬、ナスにオガラを刺して作った牛などを飾ります。この馬と牛には、先祖の霊が馬に乗ってこの世に帰り、牛に乗ってあの世に戻る、という意味が込められています。(馬に乗ってなるべく早くこの世に帰り、牛に乗ってゆっくりゆっくりあの世に戻っていただく、という意味もあるようです。)
ただし、浄土真宗では、自分の善行や施物を死者に回向する「追善供養」の思想はありません。他界した人は阿弥陀如来の本願によって浄土に往生するという教義なので、迎え火、送り火、精霊棚などは行いません。



2008年06月25日
お盆のいわれ
お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。お盆という行事は、親孝行の大切さを説いた『盂蘭盆経』というお経に由来するものです。
お釈迦さまの弟子の一人である目蓮尊者は、神通力が一番すぐれているとされていました。ある時、亡き母が餓鬼道に落ち、逆さ吊りにされて苦しんでいることを神通力によって知り、どうしたら母親を救えるか、お釈迦さまに相談に行きました。お釈迦さまは、多くの人に施しをすると母親は助かる、と言われたのです。そこで彼は教えに従い、夏の修行期間の明ける7月15日に多くの僧たちに飲食物をささげて供養したのです。すると、その功徳によって、母親は極楽往生がとげられました。
それ以来(旧暦の)7月15日は先祖に報恩感謝をささげ、供養をする日となったのです。現在、日本各地で行われているお盆の行事は、各地の風習などが加わったり、宗派による違いによりさまざまですが、一般的には先祖の霊が帰ってくると考えられています(ただし、浄土真宗は霊魂が帰ってくるという考え方はしません)。

《盆踊り》
先に述べた『盂蘭盆経』に記されていた説で、母が苦しみの餓鬼道から救われ、成仏できたことを知った目蓮尊者は、その喜びを身体中で表現しました。その姿は踊っているように見えたのです。これが「盆踊り」のはじまりとされています。最近では宗教的な意味合いは薄れてきましたが、元来、盆踊りとは帰ってきた霊を慰め、送り出すために催されてきたのです。また、帰ってきた霊が、供養のおかげで成仏できた喜びを踊りで表現しているともいわれています。
《月遅れ盆》
現在は8月15日を中心とした3~4日がお盆であることが一般的です。これを月遅れ盆と呼びます。もともとは旧暦の7月15日を中心にお盆の行事が行われていたのですが、明治になって新暦が採用されると、7月15日は当時最も多かった農家の人達の忙しい時期と重なってしまい、都合が悪く、次第に8月15日に行うようになっていったのです。
《新盆》
新盆とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆をいいます(三河地方では初盆といいます)。喪明け前にお盆に入った場合は、翌年のお盆が新盆となります。新盆は故人の霊が初めて帰ってくるという言い伝えから、一般のお盆よりもねんごろに供養をします。親戚や縁者から盆堤灯が送られ、軒先に新盆堤灯(地域によって異なるが、絵柄のない白張堤灯)を飾るのが正式だといわれています。



お釈迦さまの弟子の一人である目蓮尊者は、神通力が一番すぐれているとされていました。ある時、亡き母が餓鬼道に落ち、逆さ吊りにされて苦しんでいることを神通力によって知り、どうしたら母親を救えるか、お釈迦さまに相談に行きました。お釈迦さまは、多くの人に施しをすると母親は助かる、と言われたのです。そこで彼は教えに従い、夏の修行期間の明ける7月15日に多くの僧たちに飲食物をささげて供養したのです。すると、その功徳によって、母親は極楽往生がとげられました。
それ以来(旧暦の)7月15日は先祖に報恩感謝をささげ、供養をする日となったのです。現在、日本各地で行われているお盆の行事は、各地の風習などが加わったり、宗派による違いによりさまざまですが、一般的には先祖の霊が帰ってくると考えられています(ただし、浄土真宗は霊魂が帰ってくるという考え方はしません)。

《盆踊り》
先に述べた『盂蘭盆経』に記されていた説で、母が苦しみの餓鬼道から救われ、成仏できたことを知った目蓮尊者は、その喜びを身体中で表現しました。その姿は踊っているように見えたのです。これが「盆踊り」のはじまりとされています。最近では宗教的な意味合いは薄れてきましたが、元来、盆踊りとは帰ってきた霊を慰め、送り出すために催されてきたのです。また、帰ってきた霊が、供養のおかげで成仏できた喜びを踊りで表現しているともいわれています。
《月遅れ盆》
現在は8月15日を中心とした3~4日がお盆であることが一般的です。これを月遅れ盆と呼びます。もともとは旧暦の7月15日を中心にお盆の行事が行われていたのですが、明治になって新暦が採用されると、7月15日は当時最も多かった農家の人達の忙しい時期と重なってしまい、都合が悪く、次第に8月15日に行うようになっていったのです。
《新盆》
新盆とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆をいいます(三河地方では初盆といいます)。喪明け前にお盆に入った場合は、翌年のお盆が新盆となります。新盆は故人の霊が初めて帰ってくるという言い伝えから、一般のお盆よりもねんごろに供養をします。親戚や縁者から盆堤灯が送られ、軒先に新盆堤灯(地域によって異なるが、絵柄のない白張堤灯)を飾るのが正式だといわれています。



2008年04月08日
今日は花祭り
4月8日は「花祭り」です。「花祭り」とは仏教の行事で、お釈迦さまの誕生日をお祝いする行事のことです。別名を「仏生会(ぶっしょうえ)」「灌仏会(かんぶつえ)」とも呼ばれています。ただ旧暦の4月8日になりますので、実際には今日というわけではありません。
「花祭り」は主にご寺院さまでお寺の行事として行なわれます。スタッフブログ「永田やのこころ」の記事でもご紹介されていましたように、岡崎の覚照寺さまでは12日に「花祭り」が行なわれます。ご寺院さまでは「花御堂」と呼ばれる小さなお堂に誕生仏を置き、その仏さまにひしゃくで甘茶を注いで参拝いたします。

お釈迦さまは生まれてすぐ七歩歩き、天と地とを指をさし、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と言われたのはとても有名なお話しです。その時のお姿が誕生仏になっています。
それでは何故、誕生仏に甘茶を注ぐのでしょう。それはお釈迦さまが誕生した時に、天に竜が現れ甘露の雨を降り注ぎ、それをお釈迦さまの産湯として使ったからとか、竜が五色の香水を注いだから、などの説があります。甘茶のもととなった甘露は神さまの飲む不老不死の水だと言われていました。
いつも自分たちの歩むべき方向を導いていただける仏さまに感謝のこころを込め、甘茶を注ぎたいものですね!
「花祭り」は主にご寺院さまでお寺の行事として行なわれます。スタッフブログ「永田やのこころ」の記事でもご紹介されていましたように、岡崎の覚照寺さまでは12日に「花祭り」が行なわれます。ご寺院さまでは「花御堂」と呼ばれる小さなお堂に誕生仏を置き、その仏さまにひしゃくで甘茶を注いで参拝いたします。

お釈迦さまは生まれてすぐ七歩歩き、天と地とを指をさし、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と言われたのはとても有名なお話しです。その時のお姿が誕生仏になっています。
それでは何故、誕生仏に甘茶を注ぐのでしょう。それはお釈迦さまが誕生した時に、天に竜が現れ甘露の雨を降り注ぎ、それをお釈迦さまの産湯として使ったからとか、竜が五色の香水を注いだから、などの説があります。甘茶のもととなった甘露は神さまの飲む不老不死の水だと言われていました。
いつも自分たちの歩むべき方向を導いていただける仏さまに感謝のこころを込め、甘茶を注ぎたいものですね!
2008年03月17日
今日はお彼岸の入り♪
お彼岸は雑節のひとつで、「暑さ寒さも彼岸まで」というように、冬の寒さは春分の日まで、夏の暑さは秋分の日までと、季節の区切りになる日でもあります。仏教用語の「彼岸」は梵語の「波羅蜜多(はらみった)」の訳で、正しくは「到彼岸(とうひがん)」と言います。つまり煩悩に満ちた此岸(しがん)を離れて涅槃(ねはん)の彼岸へ到達するという意味。現在ではお彼岸というと、年中行事の彼岸会(ひがんえ)の意味で使われます。

お彼岸は春分の日、秋分の日の中日(ちゅうにち)を挟んで前後3日間の合わせて一週間のことを言います。つまり今日17日はお彼岸の入りになります。仏の理想の世界であるこの世(此岸)の向こう岸(極楽浄土)に渡るために、それぞれの宗派の教えを守り修行に励む期間です。これは春分の日、秋分の日とも、真東から出た太陽が、極楽浄土があるとされる真西に沈む日(夕日が道しるべとなり此岸から極楽浄土へ渡る『白道(はくどう)』ができ、白道を進めば極楽浄土にいたると信じられていた)であることから始まった日本独自の行事ですので仏教行事ではありますがインドや中国にはありません。

この彼岸法要が日本で初めて行われたのは、今から約1200年前のことです。諸国にあった国分寺の僧侶が、春と秋の2回、中日(春分の日、秋分の日)を挟んで前後3日間の計7日間にわたり仏をたたえてお経をあげたと伝えられています。それから次第に一般の人にもお彼岸の法要として供養することが広まってきました。

お彼岸はお盆のように特に決まった行事や飾りつけなどはありませんが、一般的には中日やその前後に家族でお墓参りに出かけることが多いようです。また、お仏壇や墓前には季節の花や団子、おはぎなどをお供えします。 お供え物は春のお彼岸は牡丹が咲くことから牡丹餅が「ぼたもち」となり、秋のお彼岸は萩が咲く季節なので「おはぎ」となりました。

故人が亡くなってから初めてのお彼岸を「初彼岸」といい、特に手厚く供養します。家庭ではお仏壇をきれいに掃除して、毎日水と花を取り替えます。また、お彼岸の中日には、彼岸だんごを供え、線香を焚きます。できれば、自宅の仏前や墓前に壇那寺の僧侶を招き読経してもらいたいものです。僧侶を招かない場合でも、お墓参りは必ず行いたいですね。お墓には故人の好物などを供え、丁寧に供養してあげてください。
http://musashiya.n-da.jp/e32477.html

お彼岸は春分の日、秋分の日の中日(ちゅうにち)を挟んで前後3日間の合わせて一週間のことを言います。つまり今日17日はお彼岸の入りになります。仏の理想の世界であるこの世(此岸)の向こう岸(極楽浄土)に渡るために、それぞれの宗派の教えを守り修行に励む期間です。これは春分の日、秋分の日とも、真東から出た太陽が、極楽浄土があるとされる真西に沈む日(夕日が道しるべとなり此岸から極楽浄土へ渡る『白道(はくどう)』ができ、白道を進めば極楽浄土にいたると信じられていた)であることから始まった日本独自の行事ですので仏教行事ではありますがインドや中国にはありません。

この彼岸法要が日本で初めて行われたのは、今から約1200年前のことです。諸国にあった国分寺の僧侶が、春と秋の2回、中日(春分の日、秋分の日)を挟んで前後3日間の計7日間にわたり仏をたたえてお経をあげたと伝えられています。それから次第に一般の人にもお彼岸の法要として供養することが広まってきました。

お彼岸はお盆のように特に決まった行事や飾りつけなどはありませんが、一般的には中日やその前後に家族でお墓参りに出かけることが多いようです。また、お仏壇や墓前には季節の花や団子、おはぎなどをお供えします。 お供え物は春のお彼岸は牡丹が咲くことから牡丹餅が「ぼたもち」となり、秋のお彼岸は萩が咲く季節なので「おはぎ」となりました。

故人が亡くなってから初めてのお彼岸を「初彼岸」といい、特に手厚く供養します。家庭ではお仏壇をきれいに掃除して、毎日水と花を取り替えます。また、お彼岸の中日には、彼岸だんごを供え、線香を焚きます。できれば、自宅の仏前や墓前に壇那寺の僧侶を招き読経してもらいたいものです。僧侶を招かない場合でも、お墓参りは必ず行いたいですね。お墓には故人の好物などを供え、丁寧に供養してあげてください。
http://musashiya.n-da.jp/e32477.html
2008年03月10日
なーむー
先日、ある雑貨屋さまで面白いポップを見つけました。仏さまの置物に「なーむー。」と書かれたポップ。ちょっと微笑んでしまいました。
さて、この「なーむー」ですが、ご存知の通り、「南無阿弥陀仏」「南無釈迦牟尼仏」「南無妙法蓮華経」などの「南無」のこと。
では、この「南無」とはどういう意味があるのでしょう?

「南無」とは「帰依する」という意味があります。「帰依する」とは神や仏などの教えを絶対に信じ、自分を任せきることです。つまり「南無阿弥陀仏」とは阿弥陀さまの教えを絶対に信じ、自分を阿弥陀さまに任せきるということ。法事などで「南無阿弥陀仏」と唱えることはそういった意味があるのです。
さて、この「なーむー」ですが、ご存知の通り、「南無阿弥陀仏」「南無釈迦牟尼仏」「南無妙法蓮華経」などの「南無」のこと。
では、この「南無」とはどういう意味があるのでしょう?

「南無」とは「帰依する」という意味があります。「帰依する」とは神や仏などの教えを絶対に信じ、自分を任せきることです。つまり「南無阿弥陀仏」とは阿弥陀さまの教えを絶対に信じ、自分を阿弥陀さまに任せきるということ。法事などで「南無阿弥陀仏」と唱えることはそういった意味があるのです。
タグ :豆知識
2008年02月28日
東大寺は何宗のお寺?
仏教には様々な宗派があることは皆さまもご存知だと思います。この三河地方で多い宗派は真宗大谷派、そしてその本山は京都の東本願寺になります。もう少し知識のある方ですと、浄土宗の本山は?曹洞宗の本山は?と言う問いにも答えることができると思います。でも、奈良の大仏さまで有名な東大寺、その宗派を即答できる方は少ないのでは?
奈良県には有名な寺院が多いですね。たとえば先ほど申し上げた東大寺、それから法隆寺、薬師寺、唐招提寺などはとても有名です。でもそれらのお寺の宗派をすべて答えることのできる方は少ないと思います。皆さまはわかりますか?

それではさっそく回答です!
東大寺・・・・・華厳宗
法隆寺・・・・・聖徳宗
薬師寺・・・・・法相宗
唐招提寺・・・律宗
いかがでしょうか?そんな宗派なんて聞いたことがない!って方が多いのではないでしょうか?
法隆寺の聖徳宗は別ですが、華厳宗、法相宗、律宗に三論宗、成実宗、倶舎宗の3つを加え「南都六宗(なんとりくしゅう)」と言います。中学の歴史の授業で勉強したことがあると思います。これは奈良時代、平城京を中心に栄えた仏教の6つの宗派の総称で奈良仏教とも呼ばれています。
これらの宗派は民衆の救済活動に重きをおいた平安仏教や鎌倉仏教とは異なり、学派的要素が強く、仏教の教理の研究を中心に行っていた学僧衆の集まりであったため、宗派として広まることがありませんでした。そのため、「東大寺の宗派は?」と聞かれても答えることができない方が多いんですね。
自分は職業柄、京都や奈良に限らず、ご寺院さまを訪ねるのが好きなんですが、そのご寺院さまが何宗のお寺なのか、どの時代に建立されたご寺院さまなのかなどを頭に入れておいて訪ねた方がよりいっそうお寺の趣きを感じることができると思いますよ♪
奈良県には有名な寺院が多いですね。たとえば先ほど申し上げた東大寺、それから法隆寺、薬師寺、唐招提寺などはとても有名です。でもそれらのお寺の宗派をすべて答えることのできる方は少ないと思います。皆さまはわかりますか?

それではさっそく回答です!
東大寺・・・・・華厳宗
法隆寺・・・・・聖徳宗
薬師寺・・・・・法相宗
唐招提寺・・・律宗
いかがでしょうか?そんな宗派なんて聞いたことがない!って方が多いのではないでしょうか?
法隆寺の聖徳宗は別ですが、華厳宗、法相宗、律宗に三論宗、成実宗、倶舎宗の3つを加え「南都六宗(なんとりくしゅう)」と言います。中学の歴史の授業で勉強したことがあると思います。これは奈良時代、平城京を中心に栄えた仏教の6つの宗派の総称で奈良仏教とも呼ばれています。
これらの宗派は民衆の救済活動に重きをおいた平安仏教や鎌倉仏教とは異なり、学派的要素が強く、仏教の教理の研究を中心に行っていた学僧衆の集まりであったため、宗派として広まることがありませんでした。そのため、「東大寺の宗派は?」と聞かれても答えることができない方が多いんですね。
自分は職業柄、京都や奈良に限らず、ご寺院さまを訪ねるのが好きなんですが、そのご寺院さまが何宗のお寺なのか、どの時代に建立されたご寺院さまなのかなどを頭に入れておいて訪ねた方がよりいっそうお寺の趣きを感じることができると思いますよ♪
2008年02月10日
和尚さん
ご寺院さまのご住職を呼ぶとき、皆さまはどのように呼ばれていますか?その中で「和尚(おしょう)さん」と呼ばれている方も多いのでは?「和尚」とは元々戒律を授ける師をも意味すると言い、「和上」とも書かれることがあります。
日本仏教史の中で、「和上」の名前と共に知られているのは鑑真和上ですが、鑑真和上は戒律を日本に伝えるため、当時の唐から日本へとやって来ました。渡航は失敗の連続で、五度目の渡航でようやく日本へたどり着いたということはよく知られています。

754年、鑑真和上は聖武上皇、光明太后に菩薩戒を授け、さらに80人あまりの僧に具足戒、すなわち出家戒を授けました。まさに「和上」の名前に相応しい仏教の伝来者が鑑真であったのです。
ところで、「和尚」は「おしょう」「わじょう」「かしょう」と言う呼び名があり、その違いは宗派によるものというのが定説にようですが、地域での呼び名の習慣もあるのかもしれません。ちなみに「おしょう」と呼ぶのは禅宗と浄土宗になります。


日本仏教史の中で、「和上」の名前と共に知られているのは鑑真和上ですが、鑑真和上は戒律を日本に伝えるため、当時の唐から日本へとやって来ました。渡航は失敗の連続で、五度目の渡航でようやく日本へたどり着いたということはよく知られています。

754年、鑑真和上は聖武上皇、光明太后に菩薩戒を授け、さらに80人あまりの僧に具足戒、すなわち出家戒を授けました。まさに「和上」の名前に相応しい仏教の伝来者が鑑真であったのです。
ところで、「和尚」は「おしょう」「わじょう」「かしょう」と言う呼び名があり、その違いは宗派によるものというのが定説にようですが、地域での呼び名の習慣もあるのかもしれません。ちなみに「おしょう」と呼ぶのは禅宗と浄土宗になります。


タグ :豆知識
2008年02月06日
葛藤するこころ
森に入ると、葛や藤に巻きつかれた樹木を見かけることがあります。樹木が人や人生であるとすれば、「葛藤」はまとわり付く煩悩であり、やがて樹木の命すら奪いそうなちからさえ感じます。

一般的に「葛藤」とは、相反する対照的な心理状態が、その時々にしのぎを削って表面に出ようとしてせめぎ合うこころの中の状態のことを言います。
「葛藤」とは文字や言葉であると禅門では言いいます。文字に頼らず文字を超えるところに悟りの境地があるとする禅宗では、文字や言葉を「葛藤」であるとしています。ただし、禅語、すなわち公案(参禅する人たちに考えさせる問題)は禅の修行に必要不可欠なもので、「葛藤」としての文字や言葉は、これを超えるべき問題、むしろ必要な存在として考えられています。また、禅宗では葛や藤が絡み合う「葛藤」の様子を、師匠と弟子が一体となる様子にたとえています。
美味しそうなケーキが目の前に!でも、現在ダイエット中!そんなこころの中も「葛藤」なのでしょうか? (^^;)



一般的に「葛藤」とは、相反する対照的な心理状態が、その時々にしのぎを削って表面に出ようとしてせめぎ合うこころの中の状態のことを言います。
「葛藤」とは文字や言葉であると禅門では言いいます。文字に頼らず文字を超えるところに悟りの境地があるとする禅宗では、文字や言葉を「葛藤」であるとしています。ただし、禅語、すなわち公案(参禅する人たちに考えさせる問題)は禅の修行に必要不可欠なもので、「葛藤」としての文字や言葉は、これを超えるべき問題、むしろ必要な存在として考えられています。また、禅宗では葛や藤が絡み合う「葛藤」の様子を、師匠と弟子が一体となる様子にたとえています。
美味しそうなケーキが目の前に!でも、現在ダイエット中!そんなこころの中も「葛藤」なのでしょうか? (^^;)


タグ :豆知識
2008年02月04日
四苦八苦
以前、 フューネ三浦社長さまの記事 で煩悩の数は「四苦八苦」の掛け算、4×9+8×9=108であるとご紹介されました。さて、今日はその「四苦八苦」について少しお話しをしたいと思います。
実は「四苦八苦」とは、仏教における苦しみの分類のことなんです。
人生における「生」・「老」・「病」・「死」の根本的な苦しみを「四苦」といいます。そしてこの「四苦」と下記の4つの苦しみを加え八苦となります。

愛別離苦 (あいべつりく)-愛するものとわかれなければならない苦しみ

怨憎会苦 (おんぞうえく)-憎んでいる対象に出会う苦しみ

求不得苦 (ぐふとくく)-欲しいものが得られない苦しみ

五蘊盛苦(ごうんじょうく)-心身の機能が活発なため起こる苦しみ
皆さまの日常の主な苦しみはどれでしょう?どれもあまり体験したくない苦しみですよね。でも人生を歩んでいくうちには一度や二度は体験するこの苦しみ。皆さまはそんなときに何を頼りに苦しみから逃れようとしますか?それともその苦しみを正面から受け止めて自分で解決しようとしますか?どちらにしても少しでも早くその苦しみから逃れられる術を身に付けておきたいものですね。
この記事から見て楽しい記事にしようと思い、「四苦八苦」しながらちょっと頑張って手を加えてみました♪ポンポン跳ねる玉、可愛いでしょ?あれ?「四苦八苦」の使い方はこれでいいのだろうかぁ?


実は「四苦八苦」とは、仏教における苦しみの分類のことなんです。
人生における「生」・「老」・「病」・「死」の根本的な苦しみを「四苦」といいます。そしてこの「四苦」と下記の4つの苦しみを加え八苦となります。

愛別離苦 (あいべつりく)-愛するものとわかれなければならない苦しみ

怨憎会苦 (おんぞうえく)-憎んでいる対象に出会う苦しみ

求不得苦 (ぐふとくく)-欲しいものが得られない苦しみ

五蘊盛苦(ごうんじょうく)-心身の機能が活発なため起こる苦しみ
皆さまの日常の主な苦しみはどれでしょう?どれもあまり体験したくない苦しみですよね。でも人生を歩んでいくうちには一度や二度は体験するこの苦しみ。皆さまはそんなときに何を頼りに苦しみから逃れようとしますか?それともその苦しみを正面から受け止めて自分で解決しようとしますか?どちらにしても少しでも早くその苦しみから逃れられる術を身に付けておきたいものですね。
この記事から見て楽しい記事にしようと思い、「四苦八苦」しながらちょっと頑張って手を加えてみました♪ポンポン跳ねる玉、可愛いでしょ?あれ?「四苦八苦」の使い方はこれでいいのだろうかぁ?


タグ :豆知識
2008年02月01日
死別の悲しみケア
「グリーフケア」という言葉をご存知ですか?愛するひとの死は、遺されたものにとって大きなストレスであり、健康障害の原因のひとつになります。欧米では、グリーフケア(死別の悲しみケア)を予防医学として重要視しています。事前にグリーフケアを学んでいる場合、悲嘆(グリーフ)のプロセスを比較的順調に乗り切ることができるといわれています。
グリーフケアとは、大切なひとを亡くして悲しんでいるひとが立ち直っていけるように援助することです。悲しみによって起こる、怒りや自責の念などの感情・行動はどれも自然なこと。それを認めながら話しを聴いてあげましょう。慰めや励ましの言葉では癒されません。
遺族を「かわいそうなひと」と見て「何とかしてあげよう」という姿勢では、それが善意であっても、上から下への視線になります。それでは遺族も受け入れられません。その善意に感謝の言葉は返すでしょうが、こころは開きません。善意の関心であってもうるさく感じられ、敵意になることもあるといいます。不用意な勇気付けは病的なプロセスに陥らせることさえあります。
大切なひとの死に直面したときには、あまりに事が多きすぎて実感がわかず、現実感が遠のき、すぐにははっきりとした反応が出ません。すごく冷静に見えたり、逆に冷静な判断ができずパニック状態になることもあります。
その後に深い悲しみが押し寄せ、号泣や怒り・敵意、自責感などの複雑で強い感情が、次々と繰り返し表れます。故人がまだ生きているように思ったり、そう振舞うこともあります。医者などに、故人の死の原因を押し付けて敵意を向けることもあります。生前にしてやれなかったことに対して、あるいは自分が死の原因を作ってのではないかなどの自責感に襲われることも特徴です。
徐々に死を受け止められるようになることで、従来の自分の価値観や生活が意味を失って、うつ状態に陥り、自分が存在してないような無気力な状態になります。
こういった悲しみのプロセスを乗り越えて、故人のいない環境に適応して、新たな自分、新たな社会関係を築いていくのです。癒されるまでのは、個人差がありますが、配偶者の死別の場合で1~2年、子供の死別の場合は2~5年ほどと言われています。「いつまでも嘆いていてはダメだ」と叱咤することは好ましくありません。

悲しみが急速に襲ってくるのは葬儀が終り一通りの事務的な作業が終わって落ちついてからです。そのころに話し相手になったり、手紙を送ることは遺族にとって救いになります。
ひとによっては悲しみが長く続いたり、慢性化することがあります。病的な悲嘆に陥った遺族には、専門医によりカウンセリングや、薬物療法などが必要になる場合もあります。
《避けたいことば》
がんばろう・泣いてはだめ・早く元気になってね・私にはあなたの苦しみがよく理解できます・あなただけじゃない・あなたのほうがまだまし・もう立ち直れた?・ときがすべてを癒すから大丈夫・長い間苦しまなくて良かったね etc
グリーフケアとは、大切なひとを亡くして悲しんでいるひとが立ち直っていけるように援助することです。悲しみによって起こる、怒りや自責の念などの感情・行動はどれも自然なこと。それを認めながら話しを聴いてあげましょう。慰めや励ましの言葉では癒されません。
遺族を「かわいそうなひと」と見て「何とかしてあげよう」という姿勢では、それが善意であっても、上から下への視線になります。それでは遺族も受け入れられません。その善意に感謝の言葉は返すでしょうが、こころは開きません。善意の関心であってもうるさく感じられ、敵意になることもあるといいます。不用意な勇気付けは病的なプロセスに陥らせることさえあります。
大切なひとの死に直面したときには、あまりに事が多きすぎて実感がわかず、現実感が遠のき、すぐにははっきりとした反応が出ません。すごく冷静に見えたり、逆に冷静な判断ができずパニック状態になることもあります。
その後に深い悲しみが押し寄せ、号泣や怒り・敵意、自責感などの複雑で強い感情が、次々と繰り返し表れます。故人がまだ生きているように思ったり、そう振舞うこともあります。医者などに、故人の死の原因を押し付けて敵意を向けることもあります。生前にしてやれなかったことに対して、あるいは自分が死の原因を作ってのではないかなどの自責感に襲われることも特徴です。
徐々に死を受け止められるようになることで、従来の自分の価値観や生活が意味を失って、うつ状態に陥り、自分が存在してないような無気力な状態になります。
こういった悲しみのプロセスを乗り越えて、故人のいない環境に適応して、新たな自分、新たな社会関係を築いていくのです。癒されるまでのは、個人差がありますが、配偶者の死別の場合で1~2年、子供の死別の場合は2~5年ほどと言われています。「いつまでも嘆いていてはダメだ」と叱咤することは好ましくありません。

悲しみが急速に襲ってくるのは葬儀が終り一通りの事務的な作業が終わって落ちついてからです。そのころに話し相手になったり、手紙を送ることは遺族にとって救いになります。
ひとによっては悲しみが長く続いたり、慢性化することがあります。病的な悲嘆に陥った遺族には、専門医によりカウンセリングや、薬物療法などが必要になる場合もあります。
《避けたいことば》
がんばろう・泣いてはだめ・早く元気になってね・私にはあなたの苦しみがよく理解できます・あなただけじゃない・あなたのほうがまだまし・もう立ち直れた?・ときがすべてを癒すから大丈夫・長い間苦しまなくて良かったね etc
2008年01月30日
お香文化の歴史 2
この記事は 「お香文化の歴史」 の続きになります!
平安時代になると「空薫物(そらだきもの)」という言葉が使われるようになります。辞書には「どこからとも知れずかおってくるように香をたくこと」「室内や衣服・頭髪などに香をたきしめること」(大辞林より)とあり、この時代、香が仏前供養から離れて、日常空間に広がったことを知ることができます。現在の仏壇業界風に言えば、お部屋焚き香(香水香)の楽しみが空薫物に当たり、部屋に漂う香りが空薫物ということになります。
空薫物は貴族の文化そのものでもあり、貴族が身につけるべき教養でもありました。そして貴族が身にまとう香りは、その貴族の人柄でもあったのです。衣服や頭髪にたきしめられた香りに、貴族は男性も女性もここををときめかせ、顔は見えなくとも香りでその人を思い、すれ違いざまの香りに心を寄せる。そんな時代だったのですね。

鎌倉時代から室町時代になると大陸との貿易も盛んになり、交易する中で多くの香木類が日本にもたらされるようになりました。そして戦国末期から江戸時代になりと、徳川をはじめとしる大名家は香木を収集しはじめます。やがてこの風が町人の世界にも広がり、香を楽しむという流れが広い階層の人々の間に出来上がりました。


平安時代になると「空薫物(そらだきもの)」という言葉が使われるようになります。辞書には「どこからとも知れずかおってくるように香をたくこと」「室内や衣服・頭髪などに香をたきしめること」(大辞林より)とあり、この時代、香が仏前供養から離れて、日常空間に広がったことを知ることができます。現在の仏壇業界風に言えば、お部屋焚き香(香水香)の楽しみが空薫物に当たり、部屋に漂う香りが空薫物ということになります。
空薫物は貴族の文化そのものでもあり、貴族が身につけるべき教養でもありました。そして貴族が身にまとう香りは、その貴族の人柄でもあったのです。衣服や頭髪にたきしめられた香りに、貴族は男性も女性もここををときめかせ、顔は見えなくとも香りでその人を思い、すれ違いざまの香りに心を寄せる。そんな時代だったのですね。
《沈香製香炉》

鎌倉時代から室町時代になると大陸との貿易も盛んになり、交易する中で多くの香木類が日本にもたらされるようになりました。そして戦国末期から江戸時代になりと、徳川をはじめとしる大名家は香木を収集しはじめます。やがてこの風が町人の世界にも広がり、香を楽しむという流れが広い階層の人々の間に出来上がりました。


タグ :豆知識
2008年01月29日
お香文化の歴史
淡路島はお線香の産地として知られていますが、推古天皇3年(595)、その淡路島に沈香がたどり着いたことが日本における香文化の始まりとされています。「日本書紀」にはそのときの様子が次のように書かれています。
「推古天皇の三年夏四月、沈水、淡路島に漂ひ着けり。甚大き一囲、島人沈水を知らず、薪にて交てに焼く、其煙気遠く薫る、則異なりとして献る。」
(夏、淡路島へ一抱えもある沈香が流れ着いた。島民が薪として焚いたら、その煙が遠くまで良い香りを運んだ。島民はこれを不思議に思い、朝廷に奉った)

当時の日本人は香木に対しての知識をもっておらず、淡路島に漂着した香木も単なる流木として焚いてしまうが、驚くほど良い香りがしたために朝廷に奉じたというのです。この流木は聖徳太子の下に届けられ、太子は「これこそ南北の佛国に生じる栴檀香である」とし、これを彫って観音像として、余材をもって仏前で供養したという伝説もあります。香木類は東南アジアが原産地であり、日本に香木類が伝わるためには大陸との交流が必要であり、遣隋使、遣唐使をはじめとする大陸との交流によって、香木類は日本に伝わるようになりました。


「推古天皇の三年夏四月、沈水、淡路島に漂ひ着けり。甚大き一囲、島人沈水を知らず、薪にて交てに焼く、其煙気遠く薫る、則異なりとして献る。」
(夏、淡路島へ一抱えもある沈香が流れ着いた。島民が薪として焚いたら、その煙が遠くまで良い香りを運んだ。島民はこれを不思議に思い、朝廷に奉った)

当時の日本人は香木に対しての知識をもっておらず、淡路島に漂着した香木も単なる流木として焚いてしまうが、驚くほど良い香りがしたために朝廷に奉じたというのです。この流木は聖徳太子の下に届けられ、太子は「これこそ南北の佛国に生じる栴檀香である」とし、これを彫って観音像として、余材をもって仏前で供養したという伝説もあります。香木類は東南アジアが原産地であり、日本に香木類が伝わるためには大陸との交流が必要であり、遣隋使、遣唐使をはじめとする大陸との交流によって、香木類は日本に伝わるようになりました。


タグ :豆知識
2008年01月29日
お香の十徳
香りは古くから人の生活を豊かにしてきましたが、仏教では仏に香りを捧げることを重要なこととして考えてきました。この捧げる行為を供養と言いますが、香・華・灯は仏前供養の基本であり、仏壇には必ず香炉が供えられ、そこで線香などを焚きます。「香を聞くと以って佛食と為す」と説く教典もあり、香は仏や亡くなった人々の食べ物であると考えられてきました。お香は心身を清め、香り(香煙)は隅々まで行き渡り空間を清めます。また、様々な香りを味わうという楽しみも与えてくれます。
お香を扱う上で知っておきたい言葉が「香の十徳」です。「香の十徳」は11世紀の北宋の詩人、黄庭堅(こうていけん)の作で、一休禅師により日本に紹介されたとされます。

「香の十徳」
感格鬼神 清浄心身 (感は鬼神に格る、心身を清浄にし)
能除汚穢 能覚睡眠 (よく汚れを除き、よく睡眠を覚まし)
静中成友 塵裏偸閑 (静中友となり、塵裏閑の偸み)
多而不厭 寡而為足 (多くして厭はず、寡くして足れりと為し)
久蔵不朽 常用無障 (久しく蔵して朽ちず、常に用いて障り無し)
以上の意味はおおよそ下記の通りになります。
1.感覚が鋭くなる
2.心身を清浄する
3.汚穢(おわい・汚れのこと)を除く
4.眠気を覚ます
5.静かなときには友になる
6.忙しいときも閑をもたらす
7.多く使ってもいとわない
8.少なく使っても足りる
9.永く保存しても腐らない
10.常用しても差し支えない
この「香の十徳」は香の効用を端的に、そして格調高く伝える詩文です。


お香を扱う上で知っておきたい言葉が「香の十徳」です。「香の十徳」は11世紀の北宋の詩人、黄庭堅(こうていけん)の作で、一休禅師により日本に紹介されたとされます。
《唐草香炉》

「香の十徳」
感格鬼神 清浄心身 (感は鬼神に格る、心身を清浄にし)
能除汚穢 能覚睡眠 (よく汚れを除き、よく睡眠を覚まし)
静中成友 塵裏偸閑 (静中友となり、塵裏閑の偸み)
多而不厭 寡而為足 (多くして厭はず、寡くして足れりと為し)
久蔵不朽 常用無障 (久しく蔵して朽ちず、常に用いて障り無し)
以上の意味はおおよそ下記の通りになります。
1.感覚が鋭くなる
2.心身を清浄する
3.汚穢(おわい・汚れのこと)を除く
4.眠気を覚ます
5.静かなときには友になる
6.忙しいときも閑をもたらす
7.多く使ってもいとわない
8.少なく使っても足りる
9.永く保存しても腐らない
10.常用しても差し支えない
この「香の十徳」は香の効用を端的に、そして格調高く伝える詩文です。


2008年01月27日
お位牌のこと 2
この記事は 「お位牌のこと」 の続きになります!
お位牌が庶民の間に広がったのは江戸時代になってからで、直接的には檀家制度がお位牌の普及の原動力となりました。
「先祖の年忌に僧侶を家に呼ばす、年忌には檀那寺には一通りの挨拶はするものの、寺には内緒で一族が集まったり、僧侶が来ても歓待しないものは、役所でキリシタンかどうか調べること」
これは「宗門檀那請合之掟」と呼ばれるもので、慶長13年(1608)に徳川幕府により布告されたとされるものです。先祖の年忌には僧侶を呼ぶことが江戸時代には広まり、その際の供養具としてお位牌は欠かせないものになりました。
位牌祭祀は先祖供養の中心となり、檀那寺は三十三回忌、五十回忌まで続く年回忌供養の中で檀家との絆を結びます。また、江戸時代中期には庶民も高位戒名を望むようになり、戒名の価格基準も登場し、お位牌を中心とした年回忌法要と、戒名の付与は寺院経済を支える基盤となりました。
社会制度が安定した江戸時代には家産が生まれ、家督相続の象徴がお位牌になりました。もし、お位牌という文化がなければ、日本の仏教文化はもっと違った様相になったかもしれません。位牌祭祀を中心とした仏壇文化を持つ地域は多く、家ごとの仏教文化が先祖供養によって形作られてきたということもよく理解できます。


お位牌が庶民の間に広がったのは江戸時代になってからで、直接的には檀家制度がお位牌の普及の原動力となりました。
「先祖の年忌に僧侶を家に呼ばす、年忌には檀那寺には一通りの挨拶はするものの、寺には内緒で一族が集まったり、僧侶が来ても歓待しないものは、役所でキリシタンかどうか調べること」
これは「宗門檀那請合之掟」と呼ばれるもので、慶長13年(1608)に徳川幕府により布告されたとされるものです。先祖の年忌には僧侶を呼ぶことが江戸時代には広まり、その際の供養具としてお位牌は欠かせないものになりました。
位牌祭祀は先祖供養の中心となり、檀那寺は三十三回忌、五十回忌まで続く年回忌供養の中で檀家との絆を結びます。また、江戸時代中期には庶民も高位戒名を望むようになり、戒名の価格基準も登場し、お位牌を中心とした年回忌法要と、戒名の付与は寺院経済を支える基盤となりました。
社会制度が安定した江戸時代には家産が生まれ、家督相続の象徴がお位牌になりました。もし、お位牌という文化がなければ、日本の仏教文化はもっと違った様相になったかもしれません。位牌祭祀を中心とした仏壇文化を持つ地域は多く、家ごとの仏教文化が先祖供養によって形作られてきたということもよく理解できます。


タグ :豆知識
2008年01月27日
お位牌のこと
お位牌の形は中国儒教で祖先祭祀の時に使用される位版(いはん)・神主(しんしゅ)などに起源があるとされており、この儒教儀礼の影響を受けた禅宗が鎌倉時代の日本に伝わり、それと共にお位牌として日本でも使用されるようになりました。ただし、お位牌は祖先の霊が宿るものとされていることから、神道における依代(よりしろ)の考えが強くお位牌の機能に影響をもたらしています。
お位牌は仏壇祭祀において重要な役割を果たしており、お仏壇そのものの起源のひとつは位牌棚にあり、お仏壇とお位牌は表裏の関係にあります。また、お位牌は日本仏教の中で、死後はどこに行くのかという回答を与えてくれるものであり、先祖の霊がそこに宿る依代(よりしろ)となります。
お位牌そのものは中国儒教文化圏の中で生まれたもので、それが中国化する仏教の中で取り入れられ、日本の霊魂観や依代の思想と習合して日本に根付きました。お位牌の誕生に関しては、儒教・仏教・日本の伝統霊魂観それぞれの面から説明が可能ではありますが、江戸時代以降の普及の広さを見れば、お位牌がいかに日本の宗教観と社会にマッチしたものであり続けたかということがわかります。ちなみに、先祖の霊魂を供養するためのお位牌は、先祖観をもたないインド仏教では使用されません。国々によって祭祀の仕方も違えば、考え方も違うということですね。


お位牌は仏壇祭祀において重要な役割を果たしており、お仏壇そのものの起源のひとつは位牌棚にあり、お仏壇とお位牌は表裏の関係にあります。また、お位牌は日本仏教の中で、死後はどこに行くのかという回答を与えてくれるものであり、先祖の霊がそこに宿る依代(よりしろ)となります。
お位牌そのものは中国儒教文化圏の中で生まれたもので、それが中国化する仏教の中で取り入れられ、日本の霊魂観や依代の思想と習合して日本に根付きました。お位牌の誕生に関しては、儒教・仏教・日本の伝統霊魂観それぞれの面から説明が可能ではありますが、江戸時代以降の普及の広さを見れば、お位牌がいかに日本の宗教観と社会にマッチしたものであり続けたかということがわかります。ちなみに、先祖の霊魂を供養するためのお位牌は、先祖観をもたないインド仏教では使用されません。国々によって祭祀の仕方も違えば、考え方も違うということですね。


タグ :豆知識
2008年01月26日
戒名のこと
先日 「戒名は何故付けるのか」 の記事にたくさんのコメントをありがとうございました。戒名を授かるときの費用についてのコメントも多く、その関心の高さに驚かされました!で、今回はその戒名の歴史について少しご紹介します。
皆さまもご存知の通り、戒名の上に院号をつけると立派な戒名になり、戒名の下に大居士をつけるとさらに立派な戒名になります。現在見ることのできるこのような戒名は、戒名を受けた人の生前を偲ぶものとなっており、戒名からその人の人生や人となりがわかるように工夫されています。お医者さまであれば「医」の文字を入れたり、文章の得意な人であれば「文」の文字を入れたりといった感じです。
江戸時代から発達しはじめた戒名は、それによって身分がわかるようなシステムになっていました。大名であれば院殿号、居士や大姉号は下層階級には用いません。そんな戒名による身分差別が厳然としてありました。その一方、徐々に金銭で戒名の売買ができるようになり、金持ちの庶民は立派な戒名を求めるようになったのです。「身分に対しての見栄」が立派な戒名に対しての需要を生んだのです。
そうした社会背景とは別に、戒名は仏の世界への往生を約束するものとしても機能していました。仏の世界、即ち来世への期待は現在では考えられないほど大きく、戒名を受けることは仏の世界への往生を約束するものだったのです。
現代社会において戒名が形骸化していると思われるのは、仏の世界観や来世観、死後の世界観が失われている、俗にいう宗教離れがその一番の原因だと感じます。安心して仏の世界へと旅立つことを約束する戒名であるからこそ、戒名はこころの支えになるのではないでしょうか。

そうそう!昨晩の こちら の記事を見て、さっそく貼り付けてみました!でも、ちょっと大きすぎたので自分で少し小さめに手を加えてみましたよ♪それではブーログトップページに戻られる方は下のボタンをポチっとしてくださいねー!

皆さまもご存知の通り、戒名の上に院号をつけると立派な戒名になり、戒名の下に大居士をつけるとさらに立派な戒名になります。現在見ることのできるこのような戒名は、戒名を受けた人の生前を偲ぶものとなっており、戒名からその人の人生や人となりがわかるように工夫されています。お医者さまであれば「医」の文字を入れたり、文章の得意な人であれば「文」の文字を入れたりといった感じです。
江戸時代から発達しはじめた戒名は、それによって身分がわかるようなシステムになっていました。大名であれば院殿号、居士や大姉号は下層階級には用いません。そんな戒名による身分差別が厳然としてありました。その一方、徐々に金銭で戒名の売買ができるようになり、金持ちの庶民は立派な戒名を求めるようになったのです。「身分に対しての見栄」が立派な戒名に対しての需要を生んだのです。
そうした社会背景とは別に、戒名は仏の世界への往生を約束するものとしても機能していました。仏の世界、即ち来世への期待は現在では考えられないほど大きく、戒名を受けることは仏の世界への往生を約束するものだったのです。
現代社会において戒名が形骸化していると思われるのは、仏の世界観や来世観、死後の世界観が失われている、俗にいう宗教離れがその一番の原因だと感じます。安心して仏の世界へと旅立つことを約束する戒名であるからこそ、戒名はこころの支えになるのではないでしょうか。

そうそう!昨晩の こちら の記事を見て、さっそく貼り付けてみました!でも、ちょっと大きすぎたので自分で少し小さめに手を加えてみましたよ♪それではブーログトップページに戻られる方は下のボタンをポチっとしてくださいねー!

タグ :豆知識